6月21日は夏至だった。
柳田国男の本で読んだが(『先祖の話』だろうか)、かつて夏至には近しい死者が還って来たらしい。
昼の長さと夜の長さの消長には、4つのポイントがある。
(1)夜が最長で、昼が最短 ~ 冬至
(2)夜と昼の長さが同じ ~ 春分
(3)夜が最短で、昼が最長 ~ 夏至
(4)夜と昼の長さが同じ ~ 秋分
古代の日本人は「昼と夜の時間の長さの交替する」4つのポイントで、死者の世界と生者の世界をつなぐ扉が開くと考えた。そこで、亡くなったひとが生者のもとに還って来るというのだ。
神道ではもともと、土地神と祖神(おやがみ)の信仰を扱っていた。しかし、仏教が入って来てから、祖神の信仰を寺に分譲したのだという。現代、春分と秋分の日は「春のお彼岸」「秋のお彼岸」としてお墓参りのタイミングになっている。夏至の追悼行事は「お盆」(現代では8月13~16日)にずらされた。冬至の死者の祀りは消滅した(地方によっては残っているのだろうか)。
とはいえ、わたしもそんなにくわしいわけではない。柳田の本に書いてあったことを、記憶を頼りに述べているだけである。それでも「昼=光」と「夜=闇」がスイッチする瞬間に古代人が意識的で、「生」と「死」の境界が破れると考えたのは面白い。今回、『肥前国風土記(ひぜんのくにふどき)』の「鏡の渡(わたり)」を紹介する。死者が還って来る話だが、のちにその姿が異形となっていることが判明する。
ところで、「影」とはそもそも「光」の意味だった。
漢字の構成から考えてみよう。左側の「景」とは「風景」「景色」「景観」の「景」である。シャドー、ダークネス、ブラックの意味はまったくない。むしろ「姿」や「形」など、「目にはっきり見える何か」である。そして、この文字自体、「景浦(かげうら)」「景山(かげやま)」などという人名から明らかなように、すでに「かげ」と読むのだ。
右側の部首は「さんづくり」。「彩」の右側と同じだ。左側は「采」。「采配」の「采」なので、これが発音である。右側の「ミ」を反対に傾けたような「さんづくり」は意味を示す。手持ちの漢和辞典を引くと「これを部首にして、いろどり・模様・美しさ・飾りなどに関する意を表す字ができている」とある【註1】。「形」「彫」「彰」なども同じ部首だ。
つまり「影」という漢字字体に、ダークでブラックなイメージはそもそも存在しないのである。
香港映画など、中華圏の映画を観ると最後のクレジットで「電影公司」という文字を見かけることがある。「電影」とは「映画」のことだ。最初、わたしは「電気の影」という字面が分かるようで分からなかった。だが「影」がそもそも「光・姿・形」であるなら、「電影」は「電気で生み出された姿・形・映像=影」であろうと、すっきり理解できる【註2】。
というわけで、星影は「星の光」、月影は「月の光」、日影は「日光、太陽光線」である(「日陰」「日蔭」と区別する)。
だが、頭ではそう理解しても、感覚は追いつかない。「影」という文字、うっすらとダークでブラックな色調を帯びて見える。「明」という文字と比較すれば、なおさら「明らか」である。「明」「晴」「輝」などは、晴れやかで明るく、はなやかな色調を文字が帯びている。対して「影」「闇」「暗」などは、暗く陰鬱で、よどんだ色調なのだ。わたしだけだろうか。
しかし、その「輝(かがや)く」にも「かげ」が潜んでいるという。
「かげ」はもともと「かが」といい、「鏡」とは「影見(かがみ)」であるらしい。つまり、「姿見」(古い言い回しだが)と同じ発想の命名だというのだ。
「かが(kaga)」が「かげ(kagë)」になった。こういう「a→ë」の音韻転化は古代にはちょくちょくあり、「―a」の方が古い発音で、複合語の時にその形が残っているらしい【註3】。
「雨宿り」「雨夜」「雨漏り」(ama) →「雨」(amë)
「胸元」「胸先」「胸騒ぎ」(muna) →「胸」(munë)
「酒壺」「酒甕」「酒醤(さかしお)」(saka) →「酒」(sakë)
「船旅」「船乗り」「船酔い」(huna) →「船」(hunë)
「風向き」「風上」「風見鶏」(kaza) →「風」(kazë)
「影見(鏡)」(kaga) →「影」(kagë)
この「かが」に、名詞を動詞化する「-やく(やぐ)」という接尾語がついた(「はな―やぐ」「若―やぐ」「ささ(小々、細々)―やく」とか)。その結果、「かが―やく」=「輝く」という言葉になった。
以上の考察は、佐々木隆『日本の神話・伝説を読む―声から文字へ』(岩波新書)の受け売りである。該当箇所を引用しよう。

p172「ここで、「かがみ」という語を詳しく見てみる。大小さまざまな古語辞典に、これはもともと「影見(かがみ)」という複合語だとの説明が載っている。「かがkaga」は「かげkagë」の古形であり、それは「雨夜(あまよ)」の「あまama」が「あめamë」の古形であり、「酒壺(さかつぼ)」の「さかsaka」が「さけsakë」の古形であるのと同様である。「照り出づる月のかげに見え来(こ)ね」[二四六二]という『万葉集』の表現は、「照って空に出る月の光のなかに、(妻の姿が)見えてきてほしい」の意であり、「月のかげ」は「月の光」を意味する。こうした「かげ(光)」を含む複合語の「かがみ」は、「光見(かがみ)」つまり「光が当たった物体を映して見るもの」というのが原義だった。改めて説明するまでもなく、顔や姿が鏡に映って見えるのは、顔や姿に光が当たって明るく反射するからである。また、現代語の「影(かげ)」と同様に、光が当たった物体の背後にできる、正反対に暗い部分も、同じく「かげ」と言った。「かげ」には、「光」「影」の両義があったのである。」
佐々木隆『日本の神話・伝説を読む―声から文字へ』岩波新書/2007年6月
以上が「鏡」の語源ということなのだが、また別の解釈も読んだことがある。
吉野裕子『蛇 日本の蛇信仰』(講談社学術文庫)の「鏡餅」についての記述だ。つる草、つる植物に「かがみ」という名称があることを吉野は指摘する。その「にょろにょろと地を這う」細長いつるを蛇に、古代日本人は見立てた。蛇の古語は「かか」である。つまり、映像を反射する「鏡」とは別の意味の「蛇身(かがみ)」なのだ。「鏡餅」とはミラーやルッキング・グラスの鏡とは関係ない。二段、三段に重ねた餅の形が「とぐろを巻いた蛇」の見立てだというのである。すなわち、「蛇身(かがみ)餅」が原義という。

p124「この「カカ」追求の究極の目的は「鏡」にあり、問題は至高至純の宝器として三種の神器の筆頭を占める鏡であって、その解明が本章の主題である。
おそらく、「鏡(カガミ)」は「影見(カゲミ)」であるという従来の解釈を越えたところに、その本質を隠しているのでなかろうか。つまり、鏡は「影見」ではなく、この一群の「カカ」に属する語の一つとしてみることに、はじめてその本来の姿がうかがわれるのである。」
吉野裕子『蛇 日本の蛇信仰』講談社学術文庫/1995年5月
天皇家の三種の神器の鏡が「蛇」の象徴であるかどうか、わたしには判断できない。しかし、一般に「鏡」と「蛇」には互いに引き寄せあう「イメージの引力」がありそうだ。佐々木隆『日本の神話・伝説を読む』からの孫引きになるが、『肥前国風土記(ひぜんのくにふどき)』の「鏡の渡(わたり)」の伝説は興味深い。
大伴狭手彦(おおとものさでひこ)は、宣化天皇の命令で朝鮮半島に向かうことになった。旅の途中(松浦郡篠原村)で、美しい弟日姫子(おとひひめこ)と知り合い、結婚する。もちろん、狭手彦には任務がある。出立の日、彼は妻に自分の鏡を与える。しかし、彼女が栗川を渡るとき、贈られた鏡の緒が切れて、川底に沈んでしまう。
5日後、夜になると狭手彦によく似た男が弟日姫子のもとを訪れる。ふたりは一晩、一緒に過ごす。男は夜明けとともに帰っていく。そんなことが何夜かつづく。彼女はこれを不審に思い、男の服にこっそり紐を結びつける。朝になって紐をたどっていくと、山の上の沼にたどりつく。そこには寝ている蛇がいた。身体は人間の姿で水中に没し、頭が蛇の形で沼の岸に伏しているのだ。姫に見つかった途端、すぐに全身、人間の姿になり、次のような歌を詠んだという。
「篠原の 弟姫(おとひめ)の子そ さ一夜(ひとゆ)も 率寝(ゐね)てむしだや 家に下(くだ)さむ」~篠原の弟姫の子を、たった一夜でも共寝をした時には、家に帰してやらなければならないのか。(前掲、佐々木 p164)
ふだん自分の顔を覗く鏡には、その人物の「影」が映り込む。魂、つまり「霊」も『和名類聚抄』(わみょうるいじゅしょう/古代日本の国語辞典・百科事典)によると「かげ」だという(前掲、佐々木 p173)。よって、鏡をプレゼントすれば、贈った人の魂が相手に手渡されたことになる。中国には戦乱で離ればなれになる夫婦が、互いに鏡を割って、半分ずつ所有する「破鏡(はきょう)」の説話があったはずだ。
その鏡に結んだ緒が断ち切れ、川に落としてしまうことは、狭手彦の死を暗示するという。ただし、水中に没した鏡には彼の「霊(かげ)」が一部、託されているのだ。その「かげ」が「蛇(かが)」となって弟日姫子に会いに来た、とも解釈できるのである。
さて、このような「影=霊(かげ)」とは分身であろう。またまた孫引きで恐縮だが、『金枝篇』でおなじみのジェームズ・フレイザーは、次のように述べた。
p17「フレイザーによれば、未開人はしばしば自分の影や映像を自分の霊魂、または自分自身の生命的部分と見なしているという。ウェルタ島には人の影を槍で突いたり刀で斬ったりして、その当人を病気にすることのできる呪術師(じゅじゅつし)たちがいる。また、ネパールを旅行していたサンカラがダライ・ラマと争ったときに、自分の威力を示すために天高く舞い上がった。ところが、ダライ・ラマはその影を小刀で刺したので、サンカラはたちまち転落して頸(くび)を折ってしまったという話もある。」
河合隼雄『影の現象学』講談社学術文庫/1987年12月初版・2018年12月55刷
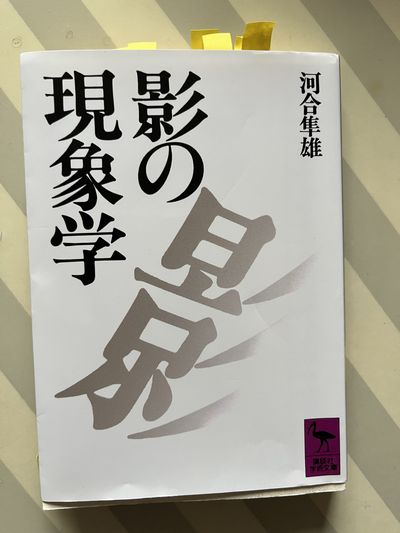
上の引用、「サンカラ」が分からない。ネットで軽く調べたが、やはりよく分からない。インド神話ではシバ神の異名を「シャンカラ」というそうだけど……。ネパール旅行するかな? ご存じの方がいれば、こっそり教えてください。お礼は出ません。
河合の『影の現象学』は「影=分身」研究の古典的名著である。
ユング派の臨床心理学者にふさわしく、民話、伝説、神話、詩、小説などから大量の「影」にまつわるエピソードを引用している。もちろん、夢も。
悪意や敵意をもった「自分=影」が登場する夢は、わたしもよく見た。おもに学生時代である。これはとんでもない悪夢であり、よく金縛りをともなった。
40年ほど前は、金縛りが脳内現象であるという説明はされていなかった。霊的現象による怪異という説明が一般的だったと記憶する。「幽霊が胸にのっかり、呼吸ができない」、「幽霊が首を絞めてきて殺されかけた」などの噂、都市伝説が流布していた。しかし、金縛り頻度の高いわたしは「これは霊現象なんかじゃない。自分のもうひとつの裏の人格が、表の人格を倒し、身体の支配権を得ようとする心理的闘争の結果だ」と考えていた。
夢の中で、わたしは屋内、室内にいる。ドアのチャイムが鳴り、訪問者が来る。ドアを開けると、見知らぬひとが立っている。男性の場合も、女性の場合もある。だいたい年齢は若く、自分と同世代だ。訪問者は最初、たいへん神妙にふるまうのだが、しだいに嫌らしくにやにや笑い出す。悪意や敵意が表情に浮かんでいる。すると突然、衝撃をともなって気づくのだ。「こいつは、おれだ! おれ自身だ」
その途端に、世界は暗転する。目の前は真っ暗。息が苦しい。呼吸ができない。全身が動かない。声が出ない。声さえ出れば身体が動くように思う。搾(しぼ)り出すように、なんとか声を出そうと気張る。しかし、まったく声は出ない。呼吸はますます苦しくなる。脅迫的な恐怖におそわれる。手足を動かし、あばれようとする。だが、まったく身体が動かない。苦しい。苦しい……。
ふとしたタイミングで声が出る。途端に、手足が動く。まるで、断絶していた脳と身体をつなぐ配線が回復したようだ。はあはあ、荒い息をつく。上半身を起こす。全身、汗まみれ。心臓は恐怖のため、早鐘のように鳴っている。アドレナリンが大量に放出されたのだろう。(もう一度、寝たらまた、あの悪夢を見るんじゃないか)と怖く、なかなか寝なおすことができない。
1989年、友人とルームシェアしていたとき、金縛りに遭った。声が出ず、苦しんだ末、なんとかようやく苦境を脱する。リビングで友人はまだ起きていて、テレビを観ていた。23時くらいだったと思う。疲労と恐怖で打ちのめされたわたしは自室を出る。よろよろリビングに顔を出した。友人は驚いた顔でこういう。
「オーモリ、なんだか、うなされていたね。うめき声がずうっとしていたよ」
じゃあ、起こせよ!
友人がピンチのときに、のうのうとテレビ観てんじゃねえよ!
と思ったものの、彼もわたしが金縛りに苦しんでいるとは予想外だったらしい。文句は、ぐっと飲み込み、(声は出ているんだな)とわたしは思った。
声が出ているが、わたしには聞こえないのだ。うめいているとき、わたしはまだ寝ており、完全に覚醒していないのだろう(覚醒に近づいているけど)。ひょっとしたら、手足も動いており、寝返りを激しくくり返しているのかもしれない。しかし、脳がその動作を確認できないのかも。金縛りは、脳と身体の神経の断絶(なかば断絶か)。脳が覚醒しかけているのに、身体が寝ている状態だろうか。覚醒しかけた脳は、まず肺に信号を送る。なぜなら、呼吸の深さが違うからだ。睡眠モードの脳や身体は酸素をそれほど必要としない。そのため、肺の運動が低レベルで維持される。しかし、覚醒モードになると、脳は大量の酸素を必要とする。そこで肺の運動レベルを高める指令を出す。しかし、脳と身体の神経伝達が断絶しているから、肺に信号が伝わらない。脳は息苦しい。必要な酸素が提供されない。それでひとによっては、誰かに首を絞められているストーリーを創造し、状況との合理化を図る。
わたしは当時、そんなことを考えた。
あまりに頻繁に金縛りに襲われるので、しだいに「あ。今日は金縛りにかかりそうだな」と予想がつくようになった。そんなときは就寝前に、腕立て伏せを50回やった。軽く身体を動かしてから、寝る。そうするとふしぎに、金縛りを免れた。脳と身体の神経伝達を活性化するとよいのだろうか。まあ、体質によるかもしれない。他のひとにも有効かどうか、分からない。
河合隼雄によると、こういう「もうひとりの自分」は、やはり「影」のようだ。
p160「古来から悪夢の典型は、何か恐ろしい怪物が睡眠中に訪ねてくるというものである。それらはときに魔女であったり吸血鬼であったり狼男であったりする。それはときに人間か動物かさえ定かでないときもあるが、これらは普遍的な影の属性をどこかにもっている。」(同書)
こういう「影」の恐ろしさを河合は指摘するが、打ち倒したり排除したり、単純な解決策は示さない。「影」との対決は人格の成長に必要だと説くのである。ちょうどジキル(光)に対するハイド(影)のように、影の人格は抑圧された「もうひとりの自分」だという。その対決は、たいへんに苦しく、死にそうになるほど危険である。実際に、こころを病み、自殺や他殺に及ぶ患者もいるらしい。
しかし、もし光の人格と影の人格がバランスを取って統合されたら、新しい自分が生まれるという。それは「死と再生」のドラマであり、一種の通過儀礼といえそうだ。多重人格を扱った古典的名著『イヴの三つの顔』(1957)は『影の現象学』全体を通し、数多く言及される。おとなしく常識的なイヴ・ホワイトに、自由奔放で攻撃的なイヴ・ブラックという別の人格が発生する。つづいてジェーンという第三人格が登場し、ホワイトとブラックが消え失せた後、ジェーンも第四人格エヴェリンに変化していく。
p270「第三人格のジェーンは自殺を企図するが助かって、そこに第四人格のエヴェリンが出現する。このエヴェリンがもっとも統合性の高い人格と思われるが、その出現の前にジェーンが自殺を企図したことについて考えてみたい。ここで、彼女の人格は急激な変化を遂げたわけであるが、このような劇的な変化は、死と再生の秘儀(ひぎ)によってこそもっとも象徴的に表現し得るものではないだろうか。死んで生まれ変わるという一般の表現がもっともぴったりとあてはまるのである。」(同書)
「死と再生」のシンボルといえば、古来から「蛇」であった。蛇の脱皮と、月の満ち欠けは古代人にとって「死と再生」のシンボルである。このことは以前も指摘した(第24回 太陽が黄色かったから/上)。
つまり、ここにも「影=蛇(かげ・かが)」の二重性が露呈する。さらにいえば、それは再生の「光(かげ)」、「輝き(かが―やき)」でもあるのだった。
さて、わたし自身は金縛りの悪夢がいつのまにか消滅し、自分の「影」もしゅるしゅると、なんだかどこかに消えてしまったようで……「死と再生」のようなドラマチックなエピソードなどなく……なんともしまりのないことになっている。(了)
(補足)アーシュラ・K・ル=グウィン『影との戦い』(「ゲド戦記Ⅰ」1968)について、河合隼雄が何か語っていないか、ちょっと本棚を捜索した。『影の現象学』では、まったく言及がなかったのだ。しかし、魔法を学ぶ少年ハイタカ(ゲド)が、自分の影とたたかうこのファンタジーは、河合の分析の格好のモデルに思える。

スタジオ・ジブリが「ゲド戦記」をアニメ映画化したとき(2007)、劇場公開時に頒布(はんぷ)した小冊子『ゲドを読む』を「発掘」した。中沢新一、河合隼雄、清水真砂子、上橋菜穂子ら、そうそうたるメンバーが当該作品について分析やコメントを寄せている。河合の「『ゲド戦記』と自己実現」という文章が、岩波書店の『図書』(1978年9月号)から再録されていた。また、監督の宮崎吾朗との対談も収録されている。
「『ゲド戦記』と自己実現」で、河合は「影」の分析を投げ出している印象を受ける。ル=グウィン本人がユングをそうとう読みこんでおり、分析が容易すぎ、食指がまったく動かないようだ。刊行当時は新鮮だった「影」の扱い方も、その後、似たような作品がぞくぞくと書かれ、「今さら」感もあるのだろう。
かわりに女性性と男性性の統合や、死と生との統合など、『こわれた腕輪』、『さいはての島へ』についての分析や言及に力を入れている。それらは読みごたえがある。
【註1】新字源(改訂新版)角川書店/1968年1月初版・2019年12月改訂新版3刷
【註2】ただし、中国語の「影」にも「シャドー」の意味があるらしい。手持ちの中国語辞書(東方中国語辞典/東方書店/2004年4月)によると、「影子」は「影法師」の意味とある。
【註3】ウムラウトのついた「ë」は発音が「e」と区別される。前者が「乙類のエ」、後者は「甲類のエ」。万葉仮名の詳細な研究の結果、母音の数が現代より多いことが判明している。
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon









