(上編よりつづく)
『土佐日記』は笑いと友愛にみちた地方=土佐から、空虚で暗い夜の都への絶望的な帰還を描いている。まるで竹取の翁と媼が、かぐや姫を月の世界に追いかけて、その荒廃と非情な現実を突きつけられ、絶望するかのような話だ。『竹取物語』の作者を紀貫之と指摘するつもりも、学問的能力もわたしにはない。しかし、この2作品の作者が同じような問題意識、テーマを追求していたように思えて仕方ない。
土佐に国司として下向する貫之は、幼い娘を連れていた。この幼女は任地の土佐で没した。そのため、同じ道のりで帰京する彼は亡き娘の思い出に触れながら旅路をたどることになる。「諧謔」や「冗談」が強調されがちな作品だが、実は後半は喪の雰囲気に覆われる「感傷旅行(センチメンタル・ジャーニー)」なのだ。
「男もすなる日記といふ……」という書き出しで有名で、国司である貫之たちに付き従う女性の立場になって書かれている。しかし、作者本人も途中からそんな「アバター」の存在を忘れてしまうようだし、いちいち面倒くさいから「語り手=紀貫之」で以下の文章をつづける。
最初に注目すべきは土佐出発の日付である。
p27「しはすのはつかあまりひとひのいぬのときに、かどです。」
『土佐日記 かげろふ日記 和泉式部日記 更級日記』日本古典文学大系/岩波書店/1957
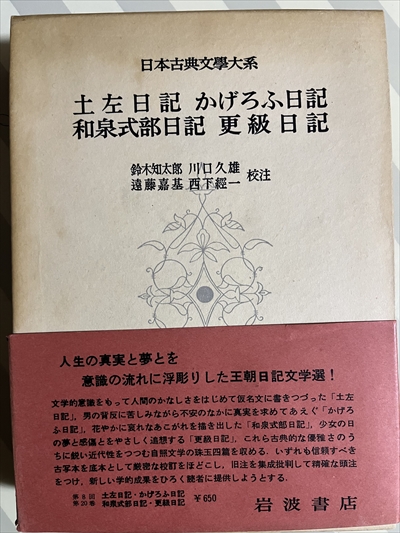
12月21日とは現代の太陽暦では冬至のころだ。太陰暦に合わせて考えると、1月末か。ここから旧暦2月16日(太陽暦では3月)の帰京にむかい、昼の時間は伸び、夜は短くなる。春にむけ、太陽の力は強まり、夜は敗北していく時期だ。
また異郷である土佐の国から、故郷の京の都へ。風や波のせいで思うにまかせぬ海路を苦労しつつ、海賊の来襲や災難に恐れながら少しずつ、55日かけて、華やかな政治・文化の中心地へ帰還する話だ。
時間的には闇から光へ。寒から暖へ。春の中心にむかう物語。空間的にも地方から中央へ。ひなびた土地から優雅と繊細の文明世界へ。時間・空間の移動において、貫之はネガティブな世界からポジティブな世界へむかっている。ところが、読んだことのあるひとは分かると思うが、「太陽」への言及がまったくない。出てくるのはひたすら「月」「月」「月」……。そして帰京した瞬間、貫之は自分が悲劇の中心に立ちつくしていることに気づき、愕然とするのだ。喜ばしいはずの帰京=帰宅が、決定的な悲嘆、絶望になる。彼にとっての都=娘のいる我が家が完全に失われていることを自覚する。ホメロスの『オデュッセイア』ではなく、むしろ『猿の惑星』のラストシーンである。
冒頭は帰京のよろこびに満ちている。貫之がどんな行政官(国司)だったか知らない。しかし、土佐の知人らは盛んに送別会を開き、酒を飲み、歌をうたい、別れを惜しむ。良好な人間関係を築いたのだろう。ふざけた描写が多発する。結末を知っていると、このままいっそ土佐にいた方がよかったのではないかと思う。諧謔と笑いに満ちたこの部分は『竹取』の前半部と対応している。
ところが12月27日。実際に船に乗り、大津から浦戸へむかう記述で、亡児への追懐が述べられる。
p29「みやこへとおもふをもののかなしきは かへらぬひとのあればなりけり」
「あるものと わすれつつ なほ なきひとを いづらと とふぞ かなしかりける」
(同書)
「都へと帰れるとうれしく思うが一方で悲しいのは、帰らない我が子がいるからなのだなあ」
「その不在を忘れるほど、いるのが当然に思え、存在しない我が子を『どこにいたっけ』とやはり問いかけてしまうのは、なんと悲しいことか」
「都へ」と思うのはうれしい。しかし、亡くなった娘と一緒でないことが悲しい。その娘は不在を忘れるほど身近で、その死を無自覚に忘れてしまう。このシーンの「夜」や「闇」の記述は「月」や「花=波の泡」の自然描写と溶け合う。「月」と「いなくなった娘」は連想を自然に『竹取』につなげる。
そして、1月11日。はね(羽根)に到着する。同行の少女が次の歌をよむ。
p37「まことにて なにきくところ はねならば とぶがごとくに みやこへもがな」
(同書)
「ほんとうに、名前に聞いた通り『羽根』ならば、飛ぶように都へはやく帰りたい」
この地名の「羽根」とは、『竹取』にからめて考えるなら「天の羽衣」である。このときから、貫之一行の乗船した船は「鳥」の属性をまとうのである。そして地上(土佐)から天空(海)を飛び去り、天界=月(都)へむかう。
p40「みなそこの つきのうへより こぐふねの さをにさはるは かつらなるらし」
「かげみれば なみのそこなる ひさかたの そらこぎわたる われぞわびしき」
(同書)
「海水の表面に反射した月の上から漕ぐ船の棹(さお)にさわるのは月の桂であるらしい」
「海面に反射した月の姿をみると、波の底にひろがる夜空を漕いで渡っている自分が切ない」
「月には桂の木が生えている」という中国の伝説(酉陽雑爼など)を踏まえた歌だ。実際には海藻に棹がからまっているのだろうか。ここに「桂」が登場するのは、結末への伏線。京には桂川が流れているからである。つまり、月とは都であり、望郷のイメージで「桂」が利用されている。あわせて、海が夜空に見立てられ、船は「鳥」となって飛んでいる。
月と望郷のイメージは、1月20日の、阿倍仲麻呂のエピソードで補強される。
p42「あをうなばら ふりさけみれば かすがなる みかさのやまに いでしつきかも」
(同書)
「あおい海原を振り仰いで見上げるとこの異郷の空に月が見える。その月はかつて故郷の春日の三笠の山からのぼった、あの月と同じものなのだなあ」
「望郷の歌」として有名なこの和歌により、月(=桂)=都の連想は読者に決定づけられる。つめたく無垢に輝く月は理想的な、もうひとつの世界=異界である。『竹取』なら、そこにいなくなった娘がいるはずだった。貫之はまた、異世界へのもうひとつの入り口―「鏡」を持っていた。
2月5日。住吉まで旅がすすんだとき、貫之の妻はこう歌う。
p51「すみのえに ふねさしよせよ わすれぐさ しるしありやと つみてゆくべし」
(同書)
「住の江の岸部に船を差し寄せてください。記憶を消せるという忘れ草、効果があるか、摘んでゆきましょう」
亡き子をひたすら忘れようとするのではない。恋しい気もちをしばらく休め、再び恋ふる力としよう――そのために、住の江の岸にあるという「忘れ草」を欲しがるのだ。「忘れたい」「忘れたくない」「忘れられない」……亡くなった娘に対するこころの葛藤が、ここにある。
しかし急に波風が立ち、船は行く手を阻まれる。住吉明神は海上の守護神(和歌の神でもある)。船頭は「ほしきものぞ、おはすらん(住吉の神様には、何かほしいものがございますのでしょう)」という。貫之は幣(ぬさ)を奉納するが、風も波もおさまらない。「なほ、うれしとおもひたぶべきもの、たいまつりたべ(もっと、もらってうれしいと思いなさるものを、差し上げてください)」と助言され、当時、貴重な「鏡」を海に投げ入れる。とたんに海は、鏡(!)のように凪ぐのである。投げ入れた「鏡」は、異界への通路を開いた。貫之は望郷の、京の都へ入る。
「かつらがは、つきのあかきにぞ わたる(桂川を、月の明るい夜に渡る)」。桂川は離京前と変わらぬ姿であった。
p57「ひさかたの つきにおひたるかつらがは そこなる影も かはらざりけり」
(同書)
「天空の月に生えている桂の木、いや、その桂ではないが、都の桂川の水底に見える月の光も以前と変わらないものだなあ」
帰京は2月16日。太陽暦で暮しているわたしたちはうっかり見逃しがちな旧暦の常識だ。旧暦は月の運行をもとにカレンダーを作っている。つまり、1月3日も4月3日も10月3日も、3日ならば必ず「三日月」なのだ。「今日は弥生の10日ほどなので、夜が明るい」などという文章も、何も考えず「ふーん。そうなんだ」と読んでしまう。だがこれももちろん「15日=満月」が近いからである。「朔日(ついたち)」も「月立ち(これから月が膨らんでいくよ!)」だし、「晦(つごもり)」も「月籠り(月が夜のむこうにこもってしまい、隠れてしまった)」である。
つまり、16日は「十六夜(いざよい)」。ほぼ満月の夜、貫之は帰京を果たす。つめたい夜の光に照らし出された、都の我が家のありさまは荒廃のきわみである。「なかがきこそあれ、ひとついへのやうなれば、のぞみてあづかれるなり(中垣こそあったが、一つの家のようなので、先方から望んで管理をまかせたのだ)」。無責任な隣人への、貫之の怒りは抑えきれない。赴任先の土佐から、ついでがあるたびごとに金品も届けさせていたという。都のこの非情、傲慢、強欲、冷淡は土佐の送別の宴といちじるしい対照をなす。5、6年の国司の任期のあいだに、1000年が過ぎたのだろうか……。
p58「おもひいでぬことなく、おもひこひしきがうちに、このいへにてうまれしをんなごのもろともにかへらねば、いかがはかなしき。……
むまれしも かへらぬものを わがやどに こまつのあるをみるが かなしき
みしひとの まつのちとせにみましかば とほくかなしき わかれせましや」
(同書)
「思い出すことばかり。その中でも思い恋しいのは、この家で生まれた娘が土佐から一緒に帰らないことなので、なんと悲しいこと。……
せっかく生まれた子どもは都に帰らないのに、帰ってみると我が家の庭に小さな松が新しく生まれている。つらい。
かつてよくかわいがって見ていた娘が、千年の寿命をもつという松のように長く面倒を見られたら、土佐での遠い悲しい別れはありえなかったなあ」
月の世界にかぐや姫はいない。そこは理想の都、我が家ではなく、打ち捨てられた廃墟である。死んだ娘が失われたことが、このとき、永遠に失われたことが、ようやく貫之にとって決定的になる。「超越的存在=娘」の不在、死が強調され、苦い絶望や幻滅がある。都に帰るより、土佐に残っていた方が、はなやかで豊かな生活があったように読める。
もう1首、貫之の「月」にまつわる和歌を紹介する。
p198「手にむすぶ水に宿れる月影のあるかなきかの世にこそありけれ」
大岡信『紀貫之』ちくま学芸文庫/2018(原本は1971年刊行)
「手ですくった水の表面に移る月の姿。そんなふうに、美しく輝く一方、ささやかで不確かな世の中であるなあ」

この歌は貫之の絶筆であるらしい。「最近、体調がよくなくて平時の状態ではない、と源公忠(みなもとのきんただ)にこの歌を送ったが、病気は急激に重篤化し、公忠が返歌しようと思っているうちに、(貫之は)亡くなった」ようである。74歳ぐらいだという。貫之は、よかれあしかれ、月の世界の住人だった。そして、「月は無慈悲な夜の女王」であった……。
こうして、宮中貴族社会に「月」が復活する。『栄花物語』を見てみよう。傲慢な「月」たちは「夜」の側から影響力を深めていく。実質的には天皇の閨房に自分の娘を送り込むことによって、形式的には一見目立たない(はずの)外戚の立場から隠然と政治力を行使することによって。したがって、貴族の娘である中宮が、帝の御子を出産するシーンでは「太陽」と「月」がそろうことになるのだ。そもそも「巻第一」のタイトルが「月の宴」である。
藤原道長の娘、中宮彰子が敦成親王を出産したところで、「月」への言及がある。
p264「五夜はとのゝ御産養(おんうぶやしなひ)せさせ給(たまふ)。十五夜の月曇(くもり)なく、秋深き露の光にめでたき折なり。」
『栄花物語(上)』岩波古典文学大系/岩波書店/1964
「五夜は殿(藤原道長)が御産養なさる。月齢十五夜の満月の夜は雲ひとつなく、秋深い時節の露の光がすばらしい折である」

敦成親王の誕生日は9月11日。五夜の御産養は9月15日――満月となる。生まれた日を初夜とし、三夜、五夜、七夜、九夜と新生児の祝いをくり返す。現在は「御七夜」だけ慣例として残っている。
彰子に仕える紫式部も、祝いの歌をくちずさむ。
p265「珍しき光さしそふ盃(さかづき)はもちながらこそ千代をめぐらめ」
(同書)
(珍しい光のさし添った月のように、お祝いの盃はひとびとの手から手へ、欠けることなく千代もめぐるでしょう)
「盃(さかづき)」の「つき」に「月」を掛けている。「もちながら」の「もち」は「望月(もちづき)」の「もち」である。「盃は欠損しない」し、「月は永遠に満月」である。実に「月」づくしなのだ。
やがて一条帝は体調を崩し、まだ幼い敦成親王を東宮(皇位継承者)に立て、急死する。道長の孫が皇位を継承するわけだ。その半年後に新しい年を迎え(長和元年=1012年)、正月十五日、藤原道長、藤原行成らが「月」にまつわる歌をよむ。おりしも「15日」=満月だからだろう。紫式部は次のような歌をよむ。
p323「雲の上を雲のよそにて思ひやる月は変わらず天の下にて」
(同書)
「雲の上の宮中のようすを、雲のうんと下から想像するのですが、一条帝は崩御なされても、月は以前と同じように天空で輝いていますね」
紫式部日記では、敦成親王誕生に「太陽」を言及する。
p17「午の時に、空晴れて、朝日さしいでたる心地す。たひらかにおはしますうれしさの、たぐひもなきに、男(をのこ)にさへおはしましけるよろこび、いかがはなのめならむ。」
『紫式部日記』(池田亀鑑・秋山虔校注)岩波文庫/1999
(正午、空が晴れて、朝日が差しこんできたような気もちがする。彰子様には平らかに御産なされ、そのことだけでもうれしさには類例がないのに、男御子でさえいらっしゃるよろこびは、どうしてひと通りのものでしょう)
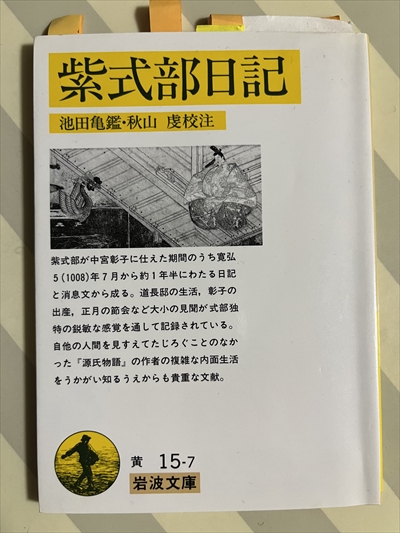
この延長線上に道長が「この世をば我が世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」を歌うことは、容易に想像できるだろう。
貴族社会=藤原摂関政治が月のシンボリズムで説明できることは、以上の思いつきによる。わたしは武家政権も同様に「月」のイメージで考えるが、例証を挙げられるほど調査がすすんでいない。ただし、「太陽」をどうやって圧倒したかは、『平家物語』で指摘できるように思う。
平家一門の政策は藤原摂関政治の踏襲だった。清盛も娘の徳子を入内させ、高倉天皇との間に御子を生ませた。したがって『竹取』同様、求婚譚・婚姻譚の文脈で「月」が太陽を超越する物語となる。
しかし、武家政権誕生のためにはもっと新しい物語と文脈が必要だった。『平家』巻第十一「那須与一」である。
p369「『あれはいかに』と見る程に、舟のうちよりよはひ十八九ばかりなる女房の、まことに優にうつくしきが、柳の五衣(いつつぎぬ)に紅の袴着て、みな紅の扇の日いだしたるを、舟のせがいにはさみたてて、陸へむいてぞまねいたる。」
『平家物語(二)』校注・訳 市古貞次/日本古典文学全集/小学館
「『あれはどういうのだろう』とみるうちに、船の中から年齢十八、九ぐらいの女房で、いかにも優雅で美しい女性が、柳の五衣(いつつぎぬ)の上に紅(くれない)の袴(はかま)を着て、紅一色の扇でまん中に金の日の丸を描いたのを、船棚にはさんで立て、陸へ向いて手招きをした。」
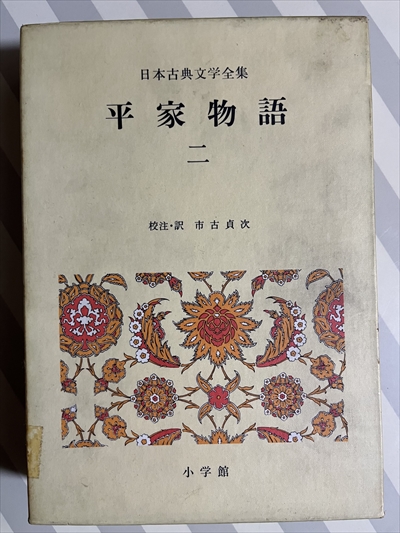
現代語訳は自分でやっていたが(下手ですみません)、ここは市古貞次の訳をそのまま載せた。「みな紅の扇の日いだしたる」を「紅一色の扇でまん中に金の日の丸を描いたの」と訳しているが、なぜなのか。たしかに、前述したように「朝日=赤」なので、原文をそのまま解釈すると「全面的に紅色の扇で、赤い日の出の太陽を描いたの」となる。背景が「紅」、日輪が「赤」では色彩デザイン的におかしい。地と図の区別がつかないだろう。しかしでは、太陽を「金色」とみなした根拠は何なのだろう?
「金色の太陽」は「黄色い太陽」に近い。このころもまだ、日本人は太陽を見上げていたのかもしれない。「太陽=赤」という認識はいまだに成立していなかったか。しかし、扇全体は「紅」なのだ。そして、このシーンの刻限は「夕方」だ。扇の「日の出」と、その舞台となる屋島の「日の入り」が重なっているのだ。
p372~373「与一鏑(かぶら)をとッてつがひ、よッぴいてひゃうどはなつ。小兵といふぢやう十二束(そく)三伏(みつぶせ)、弓は強し、浦ひびく程長鳴りして、あやまたず扇のかなめぎは一寸ばかりおいて、ひィふつとぞ射きッたる。鏑は海へ入りければ、扇は空へぞあがりける。しばしは虚空にひらめきけるが、春風に一(ひと)もみ、二(ふた)もみもまれて、海へさッとぞ散ッたりける。夕日のかかやいたるに、みな紅の扇の日いだしたるが、白波のうへにただよひ……」
(同書)
「与一は鏑矢を取って弓につがえ、十分引きしぼってひゅうっと射放した。小柄とはいうものの、矢は十二束三伏(みつぶせ)の大矢だし、弓は強弓だ。鏑矢は浦一帯に響くほど長く鳴りわたって、あやまりなく扇のかなめの際(きわ)から一寸ぐらい上を、ひいふっと射切った。しばらくは大空にひらひらひらめいたが、春風に一もみ二もみもまれて、海へさっと散ったのであった。夕日が輝いているなかに、金の日輪を描いた皆紅(みなくれない)の扇が白い波の上に漂い……」(市古貞次訳)
『大鏡』でも藤原道長は伊周と競弓(くらべゆみ)をやるが、あれは的が太陽ではない。通常の同心円状の的である。したがって、太陽のシンボリズムとは無関係。与一のエピソードは『竹取物語』と比較すべきだろう。
帝(太陽)の求婚を拒絶し月へ帰ることによって、かぐや姫は「太陽からの超越性」を示した。太陽の権威の失墜は求婚譚・婚姻譚という王朝貴族社会の文脈でシンボル化されたのだ。一方、那須与一のエピソードは「太陽の扇」を弓矢で射落とすというものである。太陽の権威失墜は、軍記物語の文脈でシンボル化される。さらに踏み込んでいうと、このエピソードは承久の乱を先取りしているのだ。
もう少し『平家物語』を探ろう。終末の「女院死去」に「月」の歌がうたわれる。
大原の寂光院で晩年を送る建礼門院徳子のもとを、後白河法皇が訪れる「大原御幸」のエピソードだ。法皇の御供だった徳大寺左大臣実定は次の和歌を庵室の柱に書きつける。
p530「いひしへは月にたとへし君なれど そのひかりなき深山辺(みやまべ)の里」
(同書)
「昔宮中におられた時は月にたとえて仰いだ君―女院―であるが、今大原の深い山辺の里ではその光もなく、暗いわびしい生活をしておられる」(市古訳)
平清盛の娘、建礼門院徳子は高倉天皇(太陽)に娶(めあわ)せられた「月の娘」であった。こうして、ひとつの月の時代が「朔日(ついたち)」から「晦(つごもり)」まで経巡ったのである。
今回も、つまらない思いつきをながながと書きつらねてしまった。お付き合いくださった方にはお礼申し上げます。
最後に、もうふたつだけ。
まず「日本以外に、太陽を赤いとみなす国はあるか」という点について。
ネットで調べてみると、タイがそうらしい。しかし、タイの歴史についてはまったくの無知、もの知らず。現代は王室があり、軍事政権が存在し、「二重権力構造」であると知っているが、それが昔からのものなのか、分からない。また、タイでは「月は何色か」突きとめられなかった。三島由紀夫の「豊饒の海」――『暁の寺』(1970)の舞台でもあり、たいへん気になっている。
次に「アメリカのシンボルは何か」。
20世紀後半以降、日本は象徴的天皇(太陽)、実務的行政政権(月)以外に、もうひとつの権威、権力を意識することになった。私見では、そのシンボル・イメージは「星」である。これはむろん、「星条旗」からの連想だと自分でも思う。日本人は昼に空を見上げない。見上げたとしても、この時に見るのは「青空」や「雲」である。
見上げるのは夜の「月」や「星」だ。そして、「月」も「星」も夜の側からわたしたちを支配しているような気がするのである。(了)
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon









