「毎日暑い、暑い」という声を耳にする。札幌市の猛暑日(最高気温摂氏35度以上を観測した日)が今年は今のところ3回。8月23日は観測史上最高の36.3度が記録された。札幌の気象台で35度以上になった日は、ここ100年で10日程度である。北海道の連続真夏日記録は38日(8月26日現在)。真夏日は最高が30度をこえた日である。たしかに暑い。
しかし、わたしは意外に平気。夏を自分なりに楽しんでいる。「クーラーの利いた部屋で涼しく、映画を観たり本を読んだり音楽を聴いたり、快適に過ごしているんでしょ?」と思われるかもしれない。いやいや、前回の「散歩」に書いた通り、ウチに扇風機はなく、クーラーはあるけど使わない。せいぜい団扇であおぐくらいだ。
どうやって涼を取っているのか? SNSでちょこちょこつぶやいているが、水風呂に入っているのだ。シャワーも真水。
1995年、関東に住んでいるころから、夏はそうやって過ごしている。クーラーを使わないから、ヒートアイランド現象に加担しない。電気もつかわない。ガスもつかわない(今年7月の使用金額は3000円以下だった。ちなみにプロパンガスである)。グレタ・トゥーンベリちゃんが何を言おうとまったく平気だ。
品川区民だったころ、夏の暑さに苦しめられたことを、前回の「散歩」に書いた。その当時、こう考えたのである。
(寒いときはどんどん着込んで厚着すればいい。しかし、暑いときには脱いでも限界がある。一般的にそういわれているし、なるほど確かにその通りだ。たとえ素っ裸になったとしても、関東地方の熱空間という巨大な厚いコートを着ている……。これを脱ぎ捨てることはできない。しかし、なにか方法があるはずだが……。あ、そうだ! 「熱/厚いコート」の下に、体温を下げる「冷たい服」を着ればいいんじゃないかな!)
だがもちろん、「着ると寒くなる服」など、当時はどこにも売っていない。
(それなら、風呂に水道水をはって、そのまま浸かればいいんじゃない?)
実際にやってみると、これがなんと快適。そもそも真夏の関東地方で水道の栓をひねって出てくるのは水ではない。「ぬるま湯」だ。冷水に浸かっているわけでないのだ。30年ほど前のことだから……今なら、きっと……ほかほかの「温水」が蛇口から出てくると思う。ガスレンジであたためなくても、そのままカップラーメンをゆでられるんじゃないかな……(?)
そんな水道水だから、もちろん飲めたものじゃない。大学時代の友人(東京在住)は「浄水器を買った」といっていた。だが、冷たくすれば飲めるのである。角氷をコップに入れれば問題解決。ふだんから水道水をアクリルピッチャー(冷水筒)に入れ、氷を足し、冷蔵庫に保存していた。咽喉がかわいたら、水道の水でなく、冷蔵庫の冷水を飲んでいた。
そんな「ぬるま湯風呂」に浸かりながら、読書する。雑貨屋で買った中国製の小さな携帯ラジオ(乾電池式。500円くらい)を、バスフロアに置く。ジャミロクワイの「ヴァーチャル・インサニティ」やYEN TOWN BANDの「Swallowtail Butterfly~あいのうた~」などが流れてくる。温水の風呂に浸かりながら本を読むと、湯気のせいでページがふやけてしまう。しかし、ぬるま湯は湯気が立たないから、ページが水分を吸収することがない。
また、数時間も浸かっていると肱(ひじ)、かかとの古い角質が、しだいにふやけてぽろぽろと取れてくるのだ。その結果、つるつる卵肌の「素肌美人」に(!)。さらに、風呂を出たり入ったりしているうちに、しだいに外気の暑さに身体が馴れてくる。暑さが苦にならなくなっていくのだ。当時、つき合っていた彼女が「涼をとる」ために、よくわたしに抱きついてきた。あんまりべたべた抱きつくので、うっとうしくなって閉口。「クール抱き枕」扱いだ。結局、その彼女を捨ててしまった。「つめたい男」である。
札幌ではさすがにそこまでではないが、東京のマンションの1室では、次のような現象が起こった。体温が下がった状態で居間の家具に触る。すると、ソファやテーブルが「体温」をもっており、あたたかいのだ。まるで犬や猫に触っているようだった。湿度も高いので、そこには「生命の気配」がかんじられる。「日本では怪談が夏に語られる」という習慣が納得できたように思った。
廊下の闇の奥などに、「なにかいる」気配がするのである。
「英国では怪談は冬に語られる」と第3回「恐怖の冬物語」で述べたと思う。北海道にいると「冬=死=恐怖」のイメージを実感的に理解できる。一方、本州以南(というか東南アジアだろうか?)では、「夏=生命=恐怖」のイメージがあるのかもしれない。
やや。また前置きが長く……(略)。以前に同じようなことを書いたが、水風呂で涼をとる方法を特に推奨はしない。わたし個人に効果があっても、ほかの方にも効果があるかどうか、わからない。熱中症が心配されるような酷暑である。クーラーを使えるなら無理せず、積極的に利用して体温を下げてほしい。また、心臓に持病があったり、体質的に虚弱だったりする場合、水風呂は体調不良を引き起こすかもしれない。東京では、たっぷり「ぬるま湯」を浴槽に入れていたが、札幌では10センチ程度しか冷水を入れていない。それで十分に、体温が下がる。各自、無理のないように、お過ごしください。
さて、毎回毎回、季節の話題から書き起こすなあ、とわれながら思う。これはきわめて日本の伝統的な文芸、文章スタイルに忠実な書き方だ。手紙は「時候のあいさつ」からはじまる。また、古今和歌集以降、勅撰和歌集も私家集も、だいたい「春夏秋冬」の季節の部立てからだ。平安朝の物語におけるボーイ・ミーツ・ガールのスタイルは、夜歩きしている男君が「庭」を見るところからはじまる。庭の草、木、花の描写があって、男君の視線はだんだん建物の方へ近づく。庭の植物はだいたい、いいかんじで手入れされておらず、少し荒れているのだが、それが風流で優雅であるらしい。季節に応じた花や木、草が丁寧に描かれる。御簾(みす)や御格子(みこうし)は一部、開放されていたり、壁が一部崩れたり。室内の「のぞき見」が都合よくできる。
そこに女君がいる。男君の視線は着物の色や質感(「くったり」「しんなり」している)から、頭髪の長さ、つや、美しさを丁寧に見て取る。この描写、やたら力が入っている。髪、髪、髪の毛。頭髪フェチか、と思うほど。対照的に顔や表情の描写はあっさり。近代(明治)以降、注目される目、瞳は「眉目(まみ)」と呼ばれ、「目の周辺」と曖昧化、朦朧(もうろう)化される。「かわいらしい」「上品」「優美」ということばで賞賛する。
比較の対象としてフローベールの『ボヴァリー夫人』(1857)を参照しよう。学生時代に読んだ本はどこかにいってしまい、手もとにあるのはなぜか、ペンギンブックスの英訳本。
青年医師のシャルル・ボヴァリーは、脚の骨を折った農夫の診察、治療のためにその家へ。その農夫の娘こそエンマである。
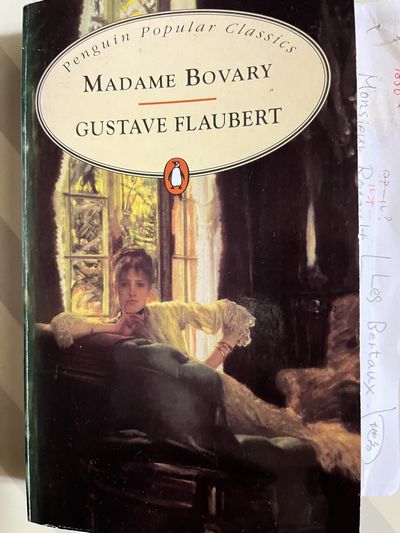
p34 One day he arrived at the farm about three o’clock. Everybody was out in the fields. He went into the kitchen, and at first failed to notice Emma; the shutters were closed. Through the chinks in the wood the sunshine came streaking across the floor in long slender lines that broke on the corners of the furniture and flickered on the ceiling. Flies were crawling over the dirty glasses on the table, buzzing as they drowned themselves in the dregs of the cider. Daylight came down the chimney, laying a velvet sheen on the sort in the fireplace and tinging the cold ashes with blue. Emma sat between the window and the heath, sewing. She had nothing round her neck, and little drops of perspiration stood on her bare shoulders.
ある日、彼(シャルル)は午後3時ごろ、農夫の家を訪れた。誰もが野良仕事に出ていた。台所から屋内へ。最初、彼はエンマに気づかなかった。よろい戸が閉まっていたのだ。だがそのよろい戸の羽目板の隙間から、細長い線となって日の光が床に注がれていた。その光線は家具の隅に当たり、反射光が天井でちかちかしている。テーブルの上の汚れたグラスの表面を蠅が這っている。リンゴ酒の飲み残しに半ば浸かり、羽をばたばたさせている。光線は煙突に降り注ぎ、暖炉のすすをビロードに輝かせ、冷たい灰を青ざめさせた。エンマは窓と火床の間に座り、縫い物をしている。首の周辺はむき出しだった。裸の両肩には小さな汗の粒が光っている。
つたない文で恐縮だが、ざっと日本語に訳してみた。英訳者の名前が確認できない。奥様のテレサ・ラッセル(Teresa Russell)さんに感謝の辞を残しているのはわかるのだけど。なぜか、ご本人のお名前を見つけられない。わたし自身の英語力不足のせいだろう。古典文学調に紹介すれば「テレサ・ラッセルの夫」(藤原道綱母のイメージ)となるか。
比較文学の論理や研究について、わたしはまったくの門外漢。したがって、日本の王朝文学とフランスのフローベール『ボヴァリー夫人』を比較し、「男主人公が女性登場人物に接近するときの、目線の動き」の彼我の違いがどの程度、明確になるのか、ちょっとわからない。例によって、とんちんかんな思いつきかもしれないが、以下、考察をすすめていく。
すぐ気づくのは、シャルルが「自然の草花」をまったく無視している点だ。農家の敷地に入る門から家屋までのアプローチに「庭」はなかったのだろうか? ないとしても、野生の草木、花が生い茂り、咲いているのではなかろうか? だが、それらはあっさり無視されるのだ。古今和歌集に季節の部立てがなく、いきなり「恋」の歌からはじまるような……。
王朝物語同様、闖入(ちんにゅう)者である男性に都合よく、建物の一部に隙間がある。話の都合上、「かいま見(のぞき見。犯罪である)」可能。そこでシャルルが目にするのは当然のように「人工物」。自然ではない。床、家具、天井、テーブル、汚れたグラス……。
そこになんと、「蠅」が登場する。「花(ハナ)」ではなく「蠅(ハエ)」! 1文字ちがうと、ずいぶんちがう。蠅は「自然」だが、平安時代の貴族の物語では注目されない。扱われるとしたら今昔物語集や宇治拾遺物語など、庶民が登場する説話文学だろう。清少納言『枕草子』では第50段「虫は」で言及される。
p179 蠅こそ、憎き物の中(うち)に、入れつべけれ。愛敬(あいぎょう)無く、憎き物は、人々しう、書き出づべき物の様に有らねど、万(よろづ)の物に居、顔などに、濡れたる足して、居たるなどよ。人の名に付きたるは、必ず、難(かた)し。
清少納言『枕草子 上』(島内裕子 校訂・訳/ちくま学芸文庫)

この「虫は」は「蓑虫(みのむし)」の説明がとりわけ有名だろう。鈴虫、松虫、蝶や蛍などを列挙し、あわれ深いものと紹介する。そして、蠅。
蠅こそ、憎たらしいもののうちに入れてしまおう。かわいげなく、憎らしいものだから、一人前に扱い、言及するにも価しないが、さまざまなものにとりつき、ひとの顔に濡れたような感触の肢で貼りつき、ぞっとする。(それなのに)ひとの名前に「蠅」が使われることがある。ありえない。
「蠅丸」「蠅彦」といった名前があったのだろうか。いずれにせよ、清少納言のいら立ちや嫌悪が伝わってくる。
この「蠅」が汚れたグラスの飲み残しに出たり入ったりし、発泡リンゴ酒を味わっているようだ。『ボヴァリー夫人』を読んだことのある方なら、これが物語全体のメタファーになっていることに気づくはず。「酒」は官能や欲望の象徴である。この「酒」は「汗」として再登場する。
つづいてまた「人工物」。煙突、暖炉、すす、灰……。その後、とうとうエンマが。髪も顔も描写されない。どんな服を着ているなんか、どうでもいい。むしろ、露出した「首まわり」や「両肩」にシャルルの視線は釘づけだ。真珠のようにきらきらしているだろう「汗」に注目する。
学生時代以来、久しぶりに再読したとき、「さすが長い間、けものの肉を食ってきたひとたちは考えることがちがうな!」などと思った。「野菜も食えよ、大事だぞ!」と。しかし、思い直してみれば、日本の王朝物語だって、女君や女房たちに対する男君のふるまいなど、大同小異だ。むしろ、王朝物語のボーイ・ミーツ・ガールのパターンは、シャルル・ボヴァリー的な欲求を巧妙に隠蔽し、「上品」「優雅」な糖衣にくるむ技巧に長けているとみなすべきだろう。表面を美しく取りつくろい、実は腹黒い。洗練された優美さは、あくまでカモフラージュだ。まったく、貴族って、いやですね。
この観点、もっと書きたいことがあるが、またまた長くなっている。シャルルがエンマの瞳にのぞきこみ、丁寧に描写するシーンもある。関心のある方は直接、テキストで確認してください。
源氏物語を題材にした森谷明子(もりやあきこ)の著作は、3作ある。
第13回鮎川哲也賞を受賞したデビュー作である『千年の黙(しじま) 異本源氏物語』(2003)、『白の祝宴 逸文紫式部日記』(2011)、『望月のあと 覚書源氏物語『若菜』』(2011)で、シリーズ3部作となる。どれも紫式部を探偵役、お付の女房、阿手木(あてき)をワトソン役に、宮中や身の回りの謎や事件を解決する形式だ。その上で、それらの謎―解明が源氏物語、紫式部日記の成立にかかわっていくことが判明する。



『白の祝宴』『望月のあと』は手もとになく、図書館の本で代用した。
さて、『千年の黙(しじま)』の冒頭では、宮中で大切にされていた「猫の消失」が事件として扱われる。サブタイトル「上にさぶらふ御猫」というフレーズは、古典文学好きなら、ピンとくるだろう。清少納言『枕草子』第7段のタイトルである。つまり、猫はそこに登場する「命婦(みょうぶ)のおとど」だ。ただし、少納言の観点では「命婦のおとど」=猫は悪役。この猫のせいで、ひどい目に遭った犬――「翁(おきな)まろ」こそ彼女が描きたかったテーマなようだ。第7段は翁まろの受難劇であり、作者はかわいそうな犬に同情をそそぐ。やさしい言葉をかける。清少納言=犬好きという印象を受けるエピソードだ。
対して、紫式部は源氏物語「若菜」の巻で、印象的な猫の使い方をしている。犬と猫。愛玩動物(ペット)としてどちらの動物に式部が愛着を示したか、わからない。しかし、源氏に犬は登場せず、猫が効果的に利用されるのである。紫式部=猫派という、清少納言との対照が成立しそうなのだ。これは、ふたりが仕えた主人である中宮彰子(左大臣・藤原道長の娘)と、中宮定子(内大臣・藤原伊周の妹)の対照をさらに明確化することになる。
まず、式部の使用人の女童(めのわらわ)「あてき」が登場する。おてんばな彼女は柿の木の上から猫の鳴き声が聞こえることに気づき、するすると木登り。しかし、枝が折れ、転落しそうになる。あわてて枝にとりすがるが、両足は宙ぶらりん。そこを、たまたま下にいた少年「岩丸」が抱き下ろす。
これまた、ボーイ・ミーツ・ガール(いや、ガール・ミーツ・ボーイ)の1パターンである。大和和紀『はいからさんが通る』(1975~1977)の花村紅緒(べにお)と伊集院忍少尉の出会い(?)が、「木登り―転落―抱きとめる」だった。そして大和といえば、源氏物語のコミック版として評価の高い『あさきゆめみし』(1979~1993)の作者ではないか! ここらへん、作者の目配せを想像し、深読みしてしまう。


式部という名前は「女房名」。女房名は本名ではない。一般に父親や男きょうだいの役職から命名される。源氏物語の作者が「式部」と呼ばれるのは、彼女の父親が式部省(宮中の人事をつかさどる)の役職を拝命していたから、と何かで読んだ記憶がある。父親の藤原為時は受領――越後守(現在の新潟県の行政長官)でもあった。彼女は中流貴族の息女である。森谷の3部作ではだいたい一貫して「香子(かおるこ)」と呼ばれる。
彼女の夫である藤原宣孝は、左大臣藤原道長に仕えている。中宮定子のもとから猫が消えた事件と時を同じくし、道長の娘・彰子のもとからも猫が行方不明になった。そのため、宣孝は「公務」として、都を駆け回り、猫探しに奔走する。香子も知恵を貸し、女童のあてきも奔走し、てんやわんやの宮廷猫騒動のおもむきだ。しかし、その猫のゆくえが明らかになってみると、男社会の権力闘争とはまた別の、女たちの秘めた物語が浮かび上がってくるのだ。
『千年の黙(しじま)』は「消失事件」「失せもの探し」が核心になっている。猫騒動のあとも、「視線の密室から消えた笛を吹く人物の謎」を解く。そして、ついに源氏物語成立に深く関わる謎を香子は解き明かすことになる。
文庫本の付記や解説でも述べられているが、源氏には「かかやく日の宮」と呼ばれる巻についての仮説が存在する。曖昧で、遠回しに説明されている光源氏と義母・藤壷の密通についての決定的描写が、この巻で活写されているのではないか、とかつて研究者が問題提起したのだ。
ウンベルト・エーコ『薔薇の名前』(1980)でも、林海象『夢見るように眠りたい』(1985)でも、洋の東西を問わず、「失われた物語」を探し出そうとする物語(後者は映画だが)は数多く作られてきた。そこには何やら神秘的で深遠な謎が横たわっていそうだ。また気が向いたら考察したい。解説で杉江松恋も触れているが、『千年』が刊行された当時、丸谷才一がだいたい同時期に『輝く日の宮』(2003/講談社)という小説を発表していた。記憶で書くが、大野晋と丸谷才一が対談形式で源氏物語を読み込み、講評していく『光源氏の物語』(1989/中央公論社)でも、丸谷が言及していたように思う。
香子の書く源氏物語は、宮中の姫君、女房たちのあいだでしだいに評判になっていく。しかし、読者たちの感想を耳にすると「しっかり描いたはずの藤壷と源氏の関係が、どうも曖昧になっているらしい」と彼女は気づきはじめる。誰かが、どこかの時点で、「かかやく日の宮」の巻を闇に葬ったようなのだ。その結果、写本(当時はすべて、手書きコピー)の流通に欠巻が生じている。
「誰」のしわざか――という主犯の名前について、作者はそんなに隠すつもりはないようだ。読んでいる最中に、多くの読者は見当がつくだろう。作者が隠蔽したいのはむしろ、従犯――実行犯である。
前回、「語りの権力性」について言及した。物語の「語り手」の社会的身分やアイデンティティが、知らず知らずのうちにテキストにおいて支配的論理や体系を形成するのだ。森谷の3部作でも、その構造は同じ。「知的で教養のある女房」が語ることが、鍵になっている。したがって、全体を通じ、「社会的権力をもつ男性貴族社会」に拮抗する「弱者とみなされる女房たち」の暗躍が語られる。
藤壷(帝の妻のひとり)が義理の息子と密通するなどという醜聞を、たとえフィクションでも許容できない権力者が、源氏物語を抹殺しようとする。義理の息子に心惹かれ、帝を裏切り、藤壷は私情を一時的に優先してしまう。
恋愛感情のない政略結婚に対する「純愛」(現代のわれわれが想像するものとはちがうけど)は可能か――そういう観点で源氏を読むことができよう。弘徽殿女御に対する桐壷更衣。権力者の後ろ盾がある「女御」に対し、何のバックボーンもない「更衣」の女性に帝が恋着すると、そこに男性貴族権力機構に対するプロテスト(抗議)が自然に仕込まれてしまうのだ。そして、それこそが源氏物語エピソードゼロ(桐壷の巻)なのである。もっとも『千年』は、そこまで踏み込んだ解釈をしていないが。
圧倒的権力、勢力の持ち主に対抗するには、物語作者の力などまったく役に立たない。まして香子は一介の受領階級の娘にすぎず、主犯の正体に思いいたったとき、彼女は絶望する。
あわせて一条帝の女御元子(げんし)のエピソードも胸を打つ。愚鈍な右大臣、藤原顕光の息女で承香殿(しょうきょうでん)の女御である。栄花物語「巻第五」でも言及される異常出産は有名だ。一条帝の妻のひとりになった元子は、一族、関係者によってひたすら懐妊が待たれる。ついに妊娠した、と周囲が知り、期待と興奮が彼女を取り巻く。「生まれるのは皇子か?」「皇女か?」「ともあれ、無事に出産してくれ!」と大騒ぎだ。
産婦人科の病院など存在しない。出産に際し、当時は僧侶が呼ばれるのだ。元子は太秦の広隆寺に運ばれ、薬師経の不断経(12人の僧侶に輪番で読経させるらしい)を読まれる。出産は一大事だ。母親も子どもも、生命の危機的状況に近づく。貴族社会において、それを安全に、スムーズに施すすべは、当時、僧侶の読経しかなかったのである。
p192 ……只事なりぬべき御けしきなれば、「さばれ、罪は後に申思はむ」と覚(おぼ)して、まかせ奉(たてまつ)り給(たまう)程に、御身よりたゞ物も覚えぬ水のさと流出(ながれい)づれば、いとあやしくよづかぬ事に人〱(ひとびと)見奉り思へど、さりとも有様(あるよう)あらむとのみ騒がせ給(たまう)に、水つきもせず出来(いでき)て、御腹たゞしゐれにしゐれて、例の人の腹よりもむげにならせ給(たまい)ぬ。
『日本古典文学大系75 栄花物語 上』松村博司・山中裕校注(岩波書店/1964)
ただ、ご出産にまちがいないご様子なので、「どうとでもなれ、神聖な寺域を出産で穢(けが)す罪は、のちにお許しを願おう」と(寺務を管理する僧侶は)思いなさり、そのままなりゆきにおまかせ申し上げなさっているうちに、(元子女御の)お身体から見たこともないような水がひたすら流れ出した。たいそう奇怪で、珍しいことと周囲のひとびとは見申しあげ、思うが、そうはいっても、何か理由があるのだろう、とひたすら騒ぎなさったところ、つきることなく水は流れつづけ、(女御の)御腹はどんどん縮んでいき、ふつうのひとの腹部よりずっとへこんでしまいなさった。
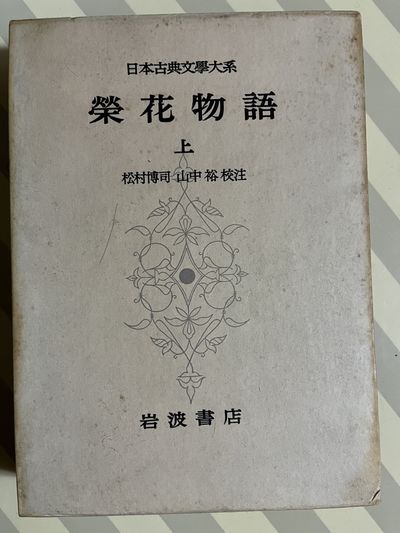
最初にこの箇所を読んだ時、わたしが連想したのは「想像妊娠」だった。帝の妻たちは、妊娠、出産への周囲の期待、プレッシャーにつねにさらされる。過度な妊娠への期待が、想像妊娠に発展したのではないか、と考えたのだ。この一件、研究者や専門家がどう言っているか、関心のある方は調べてください。岩波古典体系の補注では「腸満という病気」と解説する。「滲出性腹膜炎或いは腹水病等の如く、腹水の貯溜する疾病をいう」(服部敏良博士「平安時代医学の研究」)ということだ。1964年と、ほぼ60年前に刊行された本なので、現在もこれが通説なのかどうか、わからない(早期破水による流産とも)。
こんなスキャンダルにまみれ、すっかり意気消沈し、世をはかなんだ元子女御だが、このあと、自分なりの幸福をつかむのである。帝の妻のひとり=女御になったのは、親のため、家のためだった。つまり、自分の本心ではない。ばっちり政略結婚なのだ。男性貴族社会の権力の横暴の犠牲になったあと、したたかによみがえり、ほんとうに愛した男と添い遂げようとする――この生きざまは、「自分の生きる道を自分で選びとっていく」点で、桐壷更衣ができなかったことである。女たちの、こうした生きざまこそ、森谷の3部作に一貫して伏在しているテーマだろう。
『千年』では元子女御の思いをサポートするのが、女性よりさらに弱い、小さい、とみなされている存在なのだ。そしてこれが、失われた「かかやく日宮」の実行犯への伏線になっているのである。そして失われたことによって、源氏物語全体の運命が大きく変動する。「せいで」と「おかげで」が交錯する真相だ。ああ、これ以上くわしく書けない……。そこに、物語への信頼、物語の力への森谷の信用がある。
『白の祝宴』では、「中宮彰子が帝の子を産む」ようすを女房たちに記録させる。そしてその日記を、中宮本人が香子に編集させる。なぜ、そんな記録=日記が必要なのか。彰子はこういう。
p256~257
「わたくしはね、女たちを後世に残してやりたかったの」
中宮は微笑を浮かべている。
「今わたくしのもとに伺候している女たちは、さまざまな事情を抱えているけれど、それぞれに美点を持っている。けれど、彼女らの姿は決して人の目に触れない。そういう世界に女たちは生きている。殿方はそれぞれに日記を残し、朝廷の記録も残るでしょう。寛弘五年、九月十一日、今上第二皇子誕生。母は中宮。そして、それでおしまいよ。わたくし、仕えてくれる女たちが好きなの。困ったところもたくさんある。厄介なこともしでかす。けれど、精一杯わたくしを慕ってくれて、頼っている。産のとき、わたくしのためにどれほど祈りを捧げ、どれほど心配してくれたことか。その彼女らに報いたいのよ。その姿を、名を、この世にとどめておきたいの。だからこそ、式部、あなたに頼むのよ。女たちの細やかな情や姿を残すのに、あなたほど適任の人は、今、この世にほかにいない」
このような思いがテーマとなっているのだから、香子と藤原家氏(うじ)の長者・道長の蜜月がつづくはずがない。そもそも紫式部とは一見、単純そうに見える現象を複雑に折りたたんで解釈する傾向のあるひとだ。「栄耀栄華を達成し、めでたしめでたし」の裏側に、何かをがまんし、苦しんでいるひとがいるのではないか。ある人物の幸福は、別の誰かを虐げ、不幸にすることで成り立っているのでは。そのように考えるひとだ。それが源氏物語「若菜」の巻の女三宮降嫁のエピソードのはず。森谷は『望月のあと』でそこに言及し、3部作の幕を閉じる。
ミステリ的な衝撃度、読みごたえとしては鮎川賞を受賞した『千年の黙』がいちばんだ。しかし、『白の祝宴』『望月のあと』と読みすすめ、作者が物語に賭けた思いを受けとめたい。権力者の横車や横暴を、弱く、ささやかな者たち(わたしたち)がどうやりすごし、歪曲してはがらかし、「語り直す」のか。物語や言葉への信頼は、森谷のほかの著作からもうかがえる。
源氏物語には「年立て」の不備が指摘されている。それぞれの巻の出来事の年代と、作中人物の年齢に細かな矛盾が生じているのだ。研究者はこの現象を次のように説明する。
「物語は『桐壷』から巻を追って順番に書かれたわけではない。時間を飛び越えたエピソードが先に成立したり、巻と巻のあいだに新たなストーリーを挿入したり。したがって、年立ての矛盾は、源氏物語が成立した過程と深くかかわる。おそらく作者は途中で矛盾に気づき、修正をこころみたかもしれない。だが、すでに多くの写本が流通し、『完全版』を作成することが不可能だった。細かい瑕疵(かし)に目をつぶり、大筋が極端に破綻しなければよしとする。作者としては、そうせざるをえなかったのではないか」
わたしも、そうだったのだろうと考える。
しかし、一方でこうも思うのである。
源氏物語には、実は「語り手」がいる。この語り手は本編に目立つようにしゃしゃり出てこないが、最初から設定されているという。近代小説の「透明な神の視点」で書かれているわけでないのだ。おそらく、宮中で長年仕えた老婆――古女房だろう。こうした古参の女房が、かつて噂で耳にした、あるいは実際に体験した男君や女君の「恋の話」を若い女房に伝えるのだ。それが「いづれのおほんときにか……」という桐壷の巻の語り出しとなる。
そういう老婆の女房たちが複数人いて、それぞれ、いろいろな巻の語り手になっているという。『白の祝祭』の「日記」と同じように。そうなれば、記憶に曖昧なところもあるだろう。歪曲や失念もあるはずだ。物語全体を通して「あれはいったい、いつの時代のことだったか……」というフレーズが通奏低音になる。この設定を前提とするなら、「年立ての矛盾」は瑕疵(かし)ではない。語り手の女房たちの記憶の曖昧さを明示する、意図的なものだと解釈できる。事実関係を時系列にくっきり整理した「歴史」ではなく、「噂」や「伝説」のたぐいである。年立てが、あまりに正確で整然としていたら、むしろ逆に不自然なのだ。
p18~19
こうした光源氏のひた隠しにする行状を語り伝えたのは、いったい誰だったのだろうか。玉上琢彌(たまがみたくや)氏は、物語の語り手、ナレーターとは、光源氏のそば近くに仕える侍女たち、すなわち「女房」だと想定した。光源氏の動向を身近で見聞きした女房が、別の女房に噂話をし、それを聞いたさらに別の女房が書き留める、といった具体である。帚木巻頭では、噂話をする女房の口さがなさを、「おしゃべり」と批判しながら、その実、自分がぺらぺらと光源氏のお忍びの恋を暴露してしまう。複数の女房たちが何段階かにわたって噂を語り伝えたり筆記したりした結果、読者である我々が読んでいるという構造を物語に内在させることで、作中世界が読者の現実となだらかに繋がるという格好なのである。
高木和子『源氏物語を読む』(2021/岩波新書)
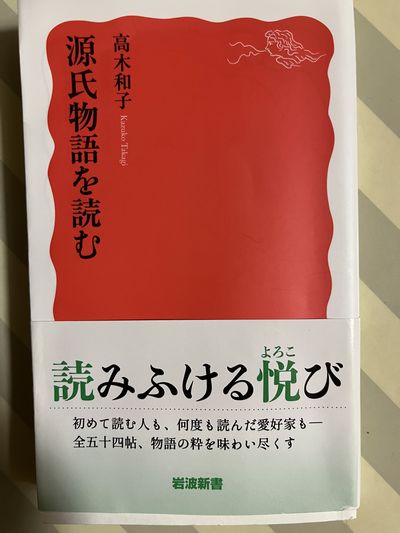
すると、源氏物語で語られている内容は「はたしてそんなことが、現実にほんとうにあったのだろうか?」という神秘性と幻想性を獲得することになる。そのように解釈し、読むことが可能なのだ。
そして、幻想性をまとったことで、月に帰ったかぐや姫のように、「手の届かない永遠性」も獲得される。「女たちの語り」は一種のミステリとなり、これからも時をこえて、語り伝えられるだろう。(了)
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon









