わたしは長編小説が好きである。
「さあ、読むぞー」と思って、コーヒーとチョコチップクッキーを用意し、19世紀西欧の分厚い翻訳小説のページを開く。ふかふかのソファにゆったり座り、両足をオットマンにのっける。巨大な虚構の世界を、頭のなかでじっくりと構築する。長い、ながーい物語にどっぷり浸かり、作品世界に深く入り込む。本を読んでいない時でも、その物語の一部になっている。街を歩いていると、通りですれ違った見知らぬ他人なのに、(はっ! 作中人物のあのひとではないか?)と思い、振り向いてしまう。いちども会ったことがない、そもそも会えるはずのない虚構の人物が、親友や恋人、家族や仇敵になる。これぞ、長編小説の醍醐味だ。
もちろん、本を読み出した子どものころは、「長編小説」という概念など意識にない。
母親は専業主婦だ。習い事(生け花、茶道、詩吟など)をよくやっていた。小学校から帰宅すると、家に誰もいない。家の鍵を所定の「隠し場所」に母親は置くことになっている。ところが、そこに鍵がない。そういう「うっかりミス」が多かった。鍵をかけ、その鍵をバッグに入れてしまうのだろう。習い事の集まり、友人や知人とのおしゃべりで頭のなかがいっぱい。学校から帰宅する息子など、どうでもいい。すっかり失念している。つまり、実の親から家を閉め出されるのだ。
ランドセルを背負って帰宅し、家の鍵が見つからないと、どうしたか?
このエッセイをお読みの方にはすぐ、推測できるはずだ。とうぜん、隣の家に行くのである。「赤の他人の家」を訪問するなど、朝飯前、お茶の子さいさいだ(?)。ましてや「ご近所さん」「お隣さん」である。玄関の掃除の最中、庭木や花に水やりしている最中に、ふつうに挨拶しているみなさんだ。アポなしの電撃訪問など、気安いご近所づきあいの一環にすぎない。
南隣が「南沢」家、北隣が「北川」家だった(どちらも仮名)。チャイムを鳴らすと、ドアを開けてくれる。
「あら。ハノンちゃん、どうしたの?」
「母さんから締め出された(ニコニコ)」
「あらあら。たいへんね。お上がんなさい。ジュースもお菓子もマンガもあるわよ」
「うん! お邪魔します(ニコニコ)」
こうしてご近所のお宅のソファにゆったり腰かけ、カルビーの「かっぱえびせん」、オレンジジュース、少年ジャンプという3点セットで楽しむ。「友好外交のため隣国を訪問した王子様」気分に浸れる。
夕方5時くらいに、恐縮した母親が迎えにくる。
「ごめんください。うちのハノンがお邪魔していませんか……?」
読みかけジャンプを小脇にかかえ、ソファから立ち上がる。
「おばさん、お迎えがきました。この雑誌、まだ途中だから、借りてもいい?」
「いいよいいよ。好きなだけどうぞ」
ジャンプは南沢さんのお宅で読み、サンデーは祖父母の家で読み、マガジンは行きつけの床屋で読んでいた。自宅ではチャンピオンを購読していたはずだ。少年キングを読む機会がなかなかなかった。
その南沢家には高校生のお兄さんがいた。ジャンプはもともと、そのお兄さんが購読しているのだ。その部屋に、おばさんに連れ込まれた(?)ことがある。書棚に小学館の児童文学全集(「少年少女世界の名作」かな)がそろっていた。「マンガばっかり読んでないで、これでも読め!」という魂胆だったのか、「この本、どれでも好きなのを読んでいいのよ~」とすすめてくれた。
「わー。すごーい。おもしろそー! 『岩窟王』や『足長おじさん』、前から読みたいなって、気になっていたんですう(ワクワク)」
などとは絶対、いわなかったはずだ。しかし、マンガに飽きたのだろうか。小学生のわたしは、その本棚の攻略に乗り出した。
『奇岩城』『岩窟王』『ああ無情』『三銃士』『ロビン・フッド』『ロビンソン・クルーソー』『ピノキオ』『ターザン』……などなど、子ども向けにアレンジされた長編読み物を読みはじめた。もちろん、短編も混ざっていた。「モルグ街の殺人」「まだらの紐」「13号独房の問題」なども読んだ記憶がある。『奇岩城』のホームズと「まだらの紐」のホームズで、キャラがずいぶん違うことに戸惑った思い出がある。「モルグ街」のデュパンとホームズがあんまり似ていて、混同していたような気もする。ギリシア神話と日本の神話で同じような話があり(オルフェウスとイザナギの冥界探訪。ヘラクレスのヒュドラ退治とスサノオのヤマタノオロチ退治)、混乱した記憶がある。自宅にポプラ社の江戸川乱歩ものがあり、それも読んでいた。わくわくドキドキしながら読むのだが、謎解きになると「子どもだと思ってバカにして!」などと腹を立てた。いやな子どもである。
小学5年生くらいで、星新一のショートショートなども読み出した覚えがある。つまり、長編も短編も分け隔てなく、雑食していたのだ。しかし、しだいに「長編の方が自分は好きだな」と思うようになった。
「長編か短編か」という問題で話題になったといえば、谷崎潤一郎と芥川龍之介の「小説の筋(プロット)」論争を思い出す。1927年の論争なので(その年の7月に芥川は自殺している)、もう約100年前の話である。

中里介山の『大菩薩峠』を評価する谷崎は、主として長編小説に見られる「構造的美観」を小説一般の特徴、美質として押し出した。筋や構造の緊密さ、起伏の面白さを好ましいものとするのだ。とうぜん、当時いわゆる「文学らしい文学=純文学」のお手本視されていた自然主義文学へのアンチテーゼだ。「身辺雑記」や「作家の経験」、文壇向けの楽屋受けのようなエッセイとも小説ともつかない「文学」が、大量に書かれていたのだ。
一方の芥川も、あまりに「工夫のない」自然主義小説には批判的だったろう。「『話』らしい話のない小説」をやんわりと否定している。少なくとも、この論争ではそのように読める。筋の面白さを「王朝もの」(宇治拾遺物語や今昔物語集にプロットを借りた)に求め、その登場人物の内面を深く掘り下げ、近代文学にバージョンアップした。しかし、自分の関心は「筋の面白さ」を超えたところにある、という。それは「燃え上がる詩的精神」だ。
こうして「谷崎=構造的美観」VS「芥川=詩的精神」という対決の構図が決定した。しかし、芥川自身、小説のプロットや筋の面白さを否定しているわけでないので、どうも守勢に立っている印象がある。彼は自らと同じように「短編の名手」と呼ばれた志賀直哉を高く評価した。同様に「名手」といわれるO・ヘンリーの短編などを読んでいたら、どう考えたかな、と思うことがある。その短編は「詩的精神」というより、筋運びの面白さに重点が置かれているようだからだ。いわゆる「短編ミステリ」と呼ばれる作品も「詩」というより、「構造」=プロットの面白さが興味の中心だろう。
一方、谷崎も「詩的精神」をなおざりにしていたとは思えない。芥川の真意を探り、「君のいう詩的精神は、だいたいどの文芸作品にはあるのではないか」と首をひねる。
ふたりの比較、対照は谷崎の「王朝もの」とでもいうべき『少将滋幹の母』(1950)を見れば、より分かりやすくなるように思う(そういう分析は、研究者によってすでにされているだろう)。

平安時代の色好みといえば在原業平だが、『平中物語』の「平中=平定文(たいらのさだふみ)」も有名だ(「貞文」とも)。彼が「本院の侍従(じじゅう)」という絶世の美女に振り回され、さんざんな目に遭う話を、芥川が「好色」(1921)という短編にまとめている。今昔物語集や宇治拾遺物語に典拠のあるこのエピソード、一編の艶笑譚(えんしょうたん)といったおもむきだ。命がけの色恋の駆け引きや奸計、奇抜なアイディアとその結末に「詩的精神」を見出せなくはない。
谷崎の『少将滋幹』も冒頭は同じような印象を受ける。しかし、いくつかのエピソードを相互に対照的に配置する(構造的美観)ことによって、「魔性の女に翻弄される色好みの貴族」「権力者の横暴と色欲」「奪い取られた若妻への妄執から逃れるためのすさまじい修行」と主題が変転し、最終的に「魔性の女」が「聖母」の顔をあらわしはじめる。「詩的精神一発!」の芥川(「好色」を書いたときはまだ29歳)に対し、戦後も生き抜き、「大家」「巨匠」となった谷崎の「小説構造の工夫」の深謀遠慮ぶりに舌を巻く。
さらにいえば、『少将滋幹』は決して、長大な長編小説ではないのである。手もとの文庫はかなり古く(消費税3パーセントで、税込240円!)、小さな活字が詰まっているが、本編はたった142ページなのだ。弦楽四重奏の室内楽でありながら、オーケストラの交響曲や長大なオペラを鑑賞したような、複雑な感興と深い感銘に打たれる。
話を戻そう。わたし個人も長編小説の「構造的美観」とやらいうものを好む。ただ、今回の「本の森散歩」では、短編を採り上げようと思うのだ。気まぐれである。芥川の主張に引き寄せ、「詩的精神」をかんじるものを選んだ。とはいえ、「詩」は各人によってピンときたり、こなかったり。きわめて主観的な芸術形態である(「芸術」そのものが鑑賞者のセンス、感性によりかかる主観的なものだが)。なにをもって「詩的精神」とするか、読み手によって感覚、認識はばらばらだろう。
たとえば、詩人が書いた短編を集めた『犯罪は詩人の楽しみ/詩人ミステリ集成』(1980/創元推理文庫/柳瀬尚紀訳/原書刊行は1967年/編者はエラリー・クイーン)は、わたしにはピンとこない。

英国最初の桂冠詩人チョーサーからはじまり、ホイットマン、ハーディ、イエーツ、キプリングと、そうそうたる名前がつらなっている。しかし、わたしがいちばん感銘を受けたのは、冒頭に配されたクイーンの「序」なのだ。
p7
「親愛なる読者諸氏へ
そっと口に出してほしい……本、という言葉を。
それをいろいろなイメージとして思い浮かべる――生命の樹、楽園の四重の川、珠玉の言葉の宝庫。
われわれの将来の希望として思い浮かべる――世界のなかの繊細な世界。
精神の目のなかに思い描く――友人、相談相手、慰め役……
こうしたことが、感謝と謙遜(けんそん)の念をこめていわれてきた。」
そもそも「モルグ街の殺人」(1841)を書いたE・A・ポオが詩人である。ミステリと詩との相性のよさは、その始原から証明されているのかもしれない(知られるように、ポオは初期SFの代表作家でもある。SFと詩だって、相性がよい。「時は準宝石の螺旋のように」「月は無慈悲な夜の女王」「世界の合言葉は森」「世界の中心で愛を叫んだけもの」「果てしなき流れの果てに」「百億の昼と千億の夜」……タイトルがもう……)。
そもそもポオの「構成の原理」を読めば、「詩的精神」と「構造的美観」を対立させて考えることがいかにナンセンスか……(ごにょごにょ)。もっとも、「鴉」には「構成の原理」をこえた「何か」をかんじるけど。
本格謎解きミステリに「詩美性」を見出すむきもある。探偵というキャラクターが、論理と詩を合致させる超越的存在だ。そういう意見も読んだことがある。また、謎解きミステリでなくても、暴力的な犯罪小説に「詩」をかんじるひとびともいる。
さてしかし、わたしが紹介したい短編集は、ミステリではないのだ。ひとつは『ラードナー傑作短編集』(1989)である。
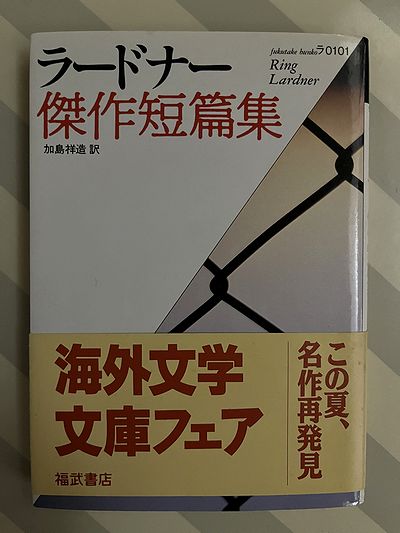
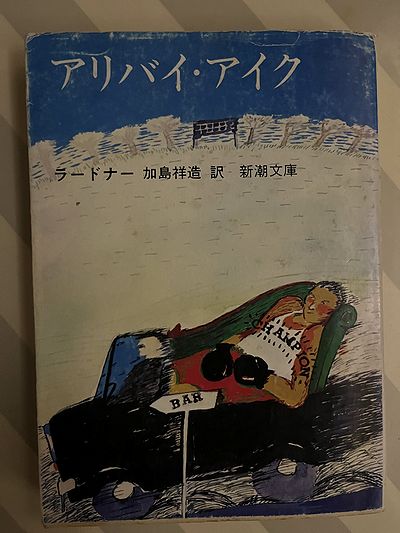
リング・ラードナーは、100年ほど前のアメリカの人気作家だ。当初はスポーツ・ライターで、野球を主とした読み物が人気だったらしい。彼の書いた「野球読み物」は全米の新聞に掲載されるほど評判になったという。当時、ハイスクールの生徒だったヘミングウェイがその文章に魅了され、「ハードボイルド」の文体を創造する上で大きな影響力を与えたとか(訳者の加島祥造の解説をもとに書いている)。『傑作短編集』の冒頭の「弁解屋(アリバイ)アイク」の粗筋を紹介しよう。
「アリバイ」は、ミステリで「現場不在証明」と訳されている。しかし、もとのラテン語では「どこかほかの場所」という意味らしい。容疑者が犯行時間に「どこかほかの場所に自分はいた」と弁解するときに、このことばが使用された。それで「弁解(する)」の意味があるという。
野球選手のフランク・X・ファレルは「弁解魔」だ。プレーに失敗したときはもちろん、成功しても弁解してばかり。チームメイトからは「アリバイ・アイク」と呼ばれる。名前は別に「アイク」ではないが。ま、あだ名とはそういうものだ。
パワーヒッターであり、そうとう打てる。打撃練習でバカスカ打つようすを見て、チームの同僚のケリーがたずねる。
p7
「去年の打率はどうだったい?」とケリーが聞いた。
「シーズンの間ずっとマラリアに罹(かか)ってたもんでねえ、結局、三割五分六厘にしかならなかったんです」
「へえ、そんなマラリアならおれも罹ってみてえな」とケリーが言ったけど、アイクは気がつかなかったそうだ。
「マラリアに罹っていた」というのはウソである。自意識過剰気味のアイクは「ほんとうの自分」を隠し、「実物以上に優秀な自分」を「アリバイ」を通して演出しようとする。そのせいか、ポーカーはやたら強い。クズのような手でも「強力なカード」がそろっているように見せかけ、大金をせしめる。だが、「すげえな」と勝負振りを対戦相手が賞賛すると、「勘ちがいしていた。強い手だと思い込んでいたんだ」と謙遜(?)するのだ。ともかく「ほんとうの自分」を隠す、隠す。
しかし、当意即妙に繰り出される「アリバイ=弁解」は用意周到なものでない。その場の思いつきを口から洩らすだけなのだ。だから、「あ、こいつウソついている」と周囲には明白なのである。前に口にした弁解を忘れるし、矛盾したことも平気でいう。
これでアイクが平凡(か、それ以下)な人物だったら、ただの「つまらない人間」「クズ」である。ところが、十分に有能で優秀なのだ。絶対に取れなさそうな外野のフライをファインプレーでキャッチする。敵投手のボールを観客席にポンポン打ち返す。おかげでチームは好成績だ。こうなれば「相手にしない」「無視」よりも、いろいろ話しかけ、ボロを出させたい。「ほんとうのアイク」を周囲は知りたくなる。興味や関心を持ってしまうのだ。しかし、それをストレートに行う=「おまえのことをもっと知りたい。本心を打ち明けてくれ」などというと、屈辱的だ。だから変化球を投げる=「からかう」ことになる。
p8
おれとケリーはやつからいろいろと聞きだしにかかった。
「うちはどこだって言ったっけ?」とおれが聞いた。
「ぼくはまだ親の家(うち)にいるんだけど、うちはカンザス・シティ――でも町のなかじゃなくて、ずっと郊外のほう」
「どうしてだい? 君ぐらい口がうまきゃ郵便局の二階にだって部屋を借りられるんじゃないか」とケリーが言った。しかしアイクは玉ネギで風邪を治すのに忙しくって答えなかった。
「奥さんがいるのかい?」とおれが尋ねた。
「いや、独身。女の子とあまりつき合わないんですよ。たまに映画や、それからパーティやダンスやローラー・スケートにゆくけど」
「女の子を拳闘の選手権試合に連れてったりしないのか?」とケリーが言った。
「そういう大きな試合はめったに来ないもの。草ボクシングばかり。第一、拳闘の試合は淑女を連れてゆくとこじゃないと思うな」
主にケリーと、語り手の「おれ」がアイクをからかう。一、二塁線で走塁手が内野手にはさまれ、なんとか盗塁を決めようとしていのに、頭上でボールが飛び交っているようだ。ケリーと「おれ」が疑問のボールを投げ合い、身体をよじってそれをアイクがかわし、塁を盗もうとしている。そのサスペンスがユーモラスに描かれるのだ。「身をよじる」ようすが、滑稽で不格好なダンスを踊っているように見えるわけである。もちろん「カンザス出身」などウソだ。ばれないように「郊外のほう」と予防線を張っている。
このアイクが、なんと恋に落ちる。相手はチーム監督の妻の妹。そうとうの美人さんだ。アイクの大活躍ぶりに彼女は興味を持ち、4人(監督、アイク、監督の妻、その妹)で食事する機会がもうけられた。話題はアイクの活躍にとうぜん、なる。彼はもちろん「弁解」をはじめる。彼女はそれを「謙遜」と勘違いした。ふたりはどんどん親密になり、デートを重ねる。この噂がチームに広まらないわけがない。そこで、よせばいいのにケリーと「おれ」がアイクをまた挟み撃ちにし、牽制球を投げ合うのだ。ところが、事態は思わぬ展開に……。
アイクは自分のウソがバレていないと思っている。だが、ケリー、「おれ」、監督、チームメイト、また読者にもバレている。つまりここには「ウソ/真実」の二重構造がずうっと存在することになる。これがきわめて音楽的なのだ。詩を考えるとき、まず音楽をイメージしてしまう。比喩やシンボルは和声感覚に近い。したがって、ウソや劇中劇も「ふたつ以上の旋律が同時に聴こえている」印象を生み出す。こういう構造は、モリエールやシェークスピアが芝居でさんざん使い倒したものだ。しかし、「野球選手」が喜劇的演出に利用されるのは今、読んでも斬新で面白い。読者はケリーや「おれ」と同じように、「ほんとうのアイク」が気になってくる。
残念ながら、現在、ラードナーの短編を入手するのは難しい。ただし、数年前に話題になった小森収編『短編ミステリの二百年1』に「笑顔がいっぱい」(1928)が収録されている。サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』の主人公ホールデン少年に「この話にほとんど死にそうになったぜ」といわせたテキストだ。小森は「この世で一番爽やかな、腐敗警官の話」と評している。卓見である。気になる方は一読を。

もうひとつ、『わが夢の女/ボンテンペㇽリ短編集』(1988)を紹介したい。マッシモ・ボンテンペㇽリは1880年代、イタリアのコモ生まれ。教師やジャーナリストの職を経て、詩人となったひとらしい。その後、小説を書きはじめる。しかし、ファシズムに関与し、晩年は不遇のうちに亡くなったという(1960年没)。訳者のひとり、岩崎純孝の「あとがき」による。
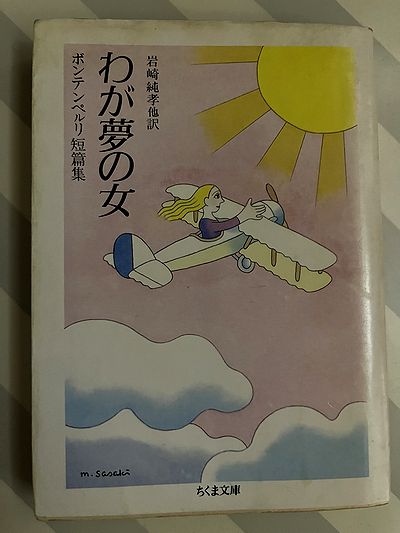
いちばん印象に残ったのは「陸と海の冒険」という1篇である。こんな話だ。
主人公で語り手の「私」はトリーノ(トリノ?)から出発する予定だ。列車の時間まで1時間、余裕がある。そこで、「カステッロ広場、スパルビーナ・ガレリーによった角」の日かげで馬車の御者を待たせ、所要を済ませにいった。すると知人の女性と偶然、再会してしまう。ふたりでレストランに入ると店は混雑している。客のひとりが、彼女を侮辱する。怒った「私」はそいつの顔をぶん殴る。お互い、瓶を片手に振りかざし、対峙する。「決闘だ!」ということになり、店の客から介添え人を探す。しかし、相手の介添え人を「馬鹿」と侮辱したため、介添え人たちも「決闘する」といい出す。そのために、あらたな介添え人が必要になり、決闘表や整理番号が用意される。
決闘場所に向かう途中、「決闘する者は死刑」という布告を新聞で知り、決闘場所を求め、外国に帆船でいくことになる。ところが夜に暴風雨になり、海賊船に襲われる。「私」以外の同乗者はみな、殺され、「私」は捕虜になる。長い航海のすえ、原住民の住む、ある島におきざりにされる。
その島の原住民の王様と対決し、勝利する。「私」は新しい王として君臨し、イタリア語で指令を発する。通じたかどうか分からないが、島は政治・文化的にどんどん向上していく。「私」は空間と時間の関係の哲学の新体系を執筆し、瓶に入れて海岸に放り投げる……。
ここまでで、文庫本の6ページ分である(全体で11ページ)。
「ばかじゃないの?」という内容だ。しかし、これがちゃんと結末を迎える(!)のである。しかも、仰天の結末だ。
ここには「構造的美観」などない。連想と思いつきを、どんどん並べているのだ。この発想は「夢」に近い。「詩的精神」に引き寄せるなら、即興詩のイメージだろう。
もう1篇、「アフリカでの私」も紹介しよう。
「いまだかつて私は、ほんとうに人殺しをしたいと思ったことはない」という物騒な書き出しからはじまる。そして、「友人のアミルカレ」を殺したことを、「私」は告白するのだ。
昔、カサブランカで、ふたりは仲良くなった。アミルカレと「私」は妙に気が合い、一緒によく酒を飲んだ。アミルカレは賭博が大好き。「私」もつき合って賭場には行く。しかし、いつも見ているだけ。賭け事にまったく興味がない。「私」には、ルッジェロ・ボンギ(誰?)の評伝を書くという野心がある。賭博にうつつを抜かしている場合ではないのだ。
あるとき、アミルカレが気まぐれに「どの数字に賭けたらいい?」と「私」に尋ねる。「36」と適当に応じる。ルーレットが回り、「36」が出る。
「次はどうしたらいい?」「もう面倒くさいな。36にそのまま置いておけよ」
再び「36」が出る。「私」は次々に数字を当てる。でたらめにいっているのに、みな当たるのだ。
狂喜乱舞のアミルカレは、それから毎晩、「私」を連れて賭場にいく。「私」に数字をいわせ、その数字に賭ける。たいへんな金額を獲得する。笑いが止まらない。
だが「私」はやはり、賭博に関心がもてない。ルッジェロ・ボンギの評伝がすすまず、いらいらしている。そこで、(こんな時間の無駄はもうおしまいだ)と決意する。頭に浮かんだ数字とちがう数字を、アミルカレに伝えるのだ。
p137
私は眼をつむって、耳と心にきいた。心から不思議な声が転(まろ)び出てささやいた。
「二十四」
そこで、アミルカレに言う。
「三十四」
小さな玉が走っている数秒が、数世紀のような気がした。私は、こうして彼を欺したことが辛かった。後悔した私は、この次は勝たしてやろうと心に誓った。玉は止まった。
三十四が出た。
この後も、脳裏に浮かんだ数字とちがう数字を「私」は口にする。しかし、口にする数字がみな的中するのだ。焦燥と困惑に「私」は襲われる。そしてついに……。
これも、たった11ページのテキストである。こういうのは、いわゆる「奇妙な味」と呼ばれる小説なのかもしれない。だが、ロアルド・ダールやジョン・コリアとはちがう。あんなふうに「理屈が通って」いない。ポスト・モダンとかマジック・リアリズムとか、そっちの方が近いように思う。ま、ジャンル分けはどうでもよい。面白ければよいのだ。
似たような作風では、マルセル・エーメを思い出すが、それはまた次回、気が向いたら採り上げることにしたい。(了)
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon









