映画が好きで、ちょくちょく観に行く。ここ数年は、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)をたのしんでいる。「アイアンマン」「キャプテン・アメリカ」など、マーベルコミックのスーパーヒーローが、さまざまな悪漢、難敵、トラブルと格闘し、ハッピーエンドにもちこむ物語だ。個人的なお気に入りは『アントマン』(2015)。「アント=蟻」のように小さくなって闘うヒーローである(巨大化することもある)。
脚本はエドガー・ライト。脱構築ゾンビ映画の『ショーン・オブ・ザ・デッド』(04)、脱構築ポリスムービーの『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン!』(07)の脚本家・監督だ。したがって、『アントマン』も脱構築スーパーヒーローものである。手に汗握るヒーローの大活躍も「サイズの問題」であり、「アント(蟻)」サイズではスパークする熱戦は線香花火、大爆発は静電気の「バチッ」程度に。それが観客のにやにや笑いを生む。
しかし、なぜかこの作品、彼は監督を途中降板している……。いったい、なにが……。ふたたび、MCUに戻ってきてほしいのだが……。
さて、無自覚に「脱構築」などと書いたことに、ここで気づいた。この言葉、まだ有効だろうか? あまり気にせず、雰囲気で「脱構築」と書いたり読んだりするのが正解だと思うので、そのまま説明なしでいく。気になる方はネットで調べてください。
MCU最新作は『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』(22)だ(いや。『ソー/ラブ&サンダー』(22)である。この原稿を最初に書いていたときは、最新作だったのだが。『ラブ&サンダー』もちろん、鑑賞ずみ)。脚本・監督はサム・ライミ。学生のころから、わたしはサム・ライミ作品を追いかけている。やはり彼のヒーローものの傑作は『ダークマン』(1990)ですよ!
遺伝子工学の研究者ペイトンは人工皮膚を開発中だ。まだ試験段階の「皮膚」は日光に当たると99分で崩壊してしまう。日夜、研究にいそしむ彼だが、悪漢どもの陰謀に巻き込まれ、研究所を爆破され、大やけどを負う。全身の40パーセントの火傷は激しい苦痛をペイトンにもたらす。医師団は患者を苦しみから救うため、視床下部の神経を切断し、すべての感覚を麻痺させる(いいのか、そんなことして?)。九死に一生を得たペイトンは皮膚の感覚を失い、壮絶な孤絶感――感覚への飢餓感をおぼえる。あわせて、理不尽な目に遭わされた激しい怒りが身内を駆け抜ける。その結果、常人には無理な怪力を発揮できるようになる(そんなバカな!)。ハンサムだった彼の顔は醜く焼けただれた。日の光のもとでは99分しかもたない「皮膚」を身にまとい、別人に変装し、悪漢たちに復讐するため、ペイトンは「ダークマン」となって暗躍をはじめる……。
なさけなく眉を寄せる主役のリーアム・ニーソンがその後、「スターウォーズ」シリーズの「ジェダイ・マスター」クワイ=ガン・ジンを演じることになるとは、当時は思ってもみなかった。
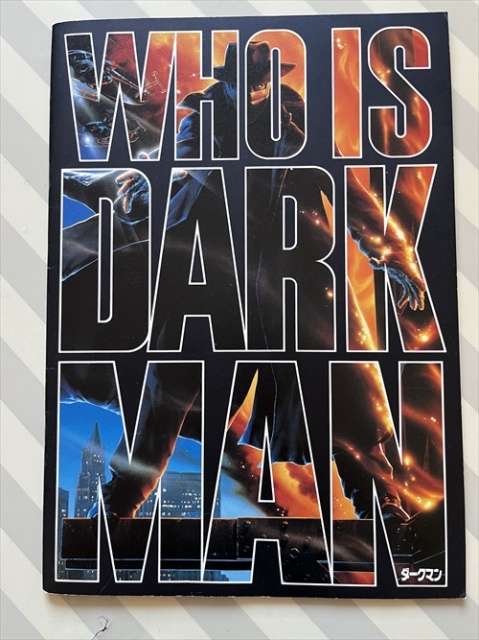

(『ダークマン』映画パンフレットより)
さて、多数のライミ作品にずっと出演している俳優がいる。ライミの出世作『死霊のはらわた』(1983)で主演したブルース・キャンベルだ。ネットの情報によると、ライミとは中学校時代からの友人であるらしい。
当然、『ドクター・ストレンジ』最新作にも出演している。マルチバースのひとつで、その「世界」の常識に無知なドクター・ストレインジ(ベネディクト・カンバーバッチ)をバカにして笑う、ピザの屋台の主人である。侮辱に腹を立てたストレンジは彼の片腕に魔法をかける。腕は持ち主の意志から離れ、勝手にこのピザ屋を殴りつづけるのだ。本筋とは無関係の、軽いコメディエピソードである。
だがこのシーン、記憶の琴線に引っかかった。
(あれ? おれはこの話を知っている。何かで読んだ……。何かで見た……)
しだいに記憶が戻ってきた。ジェラール・ド・ネルヴァル「魔法の手」(1832)である。
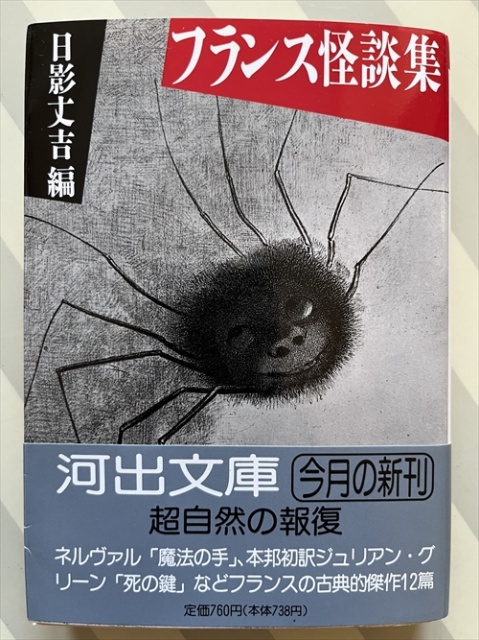
(『フランス怪談集』日影丈吉編/河出文庫)
舞台はパリ。アンリ大王の治世の末年――1600年あたりか――だ。主人公のユスターシュ・ブートルーはラシャ服飾商人。ポン・ヌフ(新橋)の上で魔術師に自分の未来を占われる。「生まれも育ちも平凡だが、最後は高く……今よりうんと高いところに昇って死ぬのだ」という。これはつまり「首吊り台に上り、処刑される」の婉曲表現である。
不吉な予言に反し、ユスターシュは結婚をひかえ、幸福の絶頂にいた。しかし、新妻から親戚の騎馬銃士を紹介される。この兵士、ことあるごとにユスターシュをからかい、バカにする。尊敬と愛情を得たいと切望する新妻の前で、特に侮辱してくる。ふだんは温厚な彼もついに、堪忍袋の緒が切れた。「決闘だ! 明日の朝、必ず来いよ!」
しかし、相手の銃士は身体的に頑健で、見ばえもよい。一方、ユスターシュは風采の上がらない平凡な町人である。とても勝ち目はない。そこで思い出したのが、ポン・ヌフの魔法使いだ。「腹にいちもつ」の魂胆を秘めたこの魔法使いは、彼の願いを聞き届け、その右腕に魔法をかける。「さ、これでもう敵がどんなに勇猛でも、その軍服に剣で無数のボタン穴を開けられるぞよ」
決闘当日、ユスターシュの腕はその意志を離れ、勝手に動き回り、最高の技量を発揮した。銃士の剣を四合で払い飛ばし、その胸板を貫いたのだ。しかし、宮廷の臣下を殺害したことの重大さにおののいた彼は、信頼している旧知の法官のもとに出向き、善後策を相談する。ところが突然、ユスターシュの腕は持ち主の意志を離れ、頼みの綱のこの法官をめった打ちに叩きつづける……。
「腕」や「手」が恐怖小説、ホラージャンルで描かれるとき、それらが究極につかむものは往々にして「死」である。かずかずのホラーアンソロジーに収録される、古典的なイギリスの恐怖小説「猿の手」(W・W・ジェイコブズ/1902)を思い出そう。「みっつの願い」型の話だ。しかし願いをかなえるために、この「手」は代償を求める。
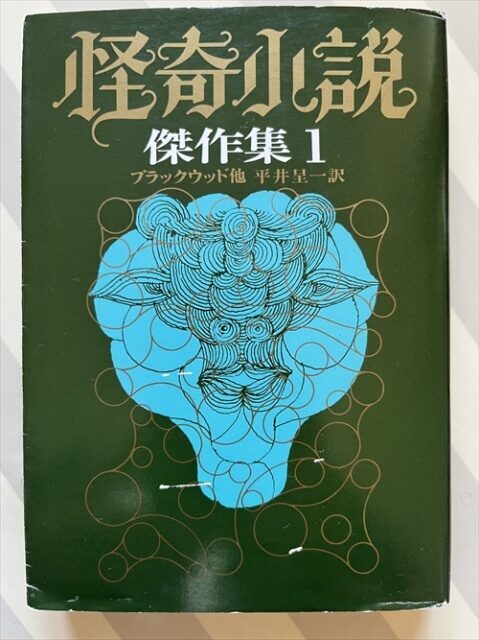
(『怪奇小説傑作集1』創元推理文庫)
呪われてしまうホワイト家に、「猿の手」を譲渡(?)したのはモリス曹長だった。曹長はインド赴任中に、土地の行者から「ミイラのように干からびた手」をもらい受けたようだ。魔術や魔法、呪いといった非合理的な恐怖が、イギリスの被支配地には渦巻いている。抑圧されている植民地は、理屈をこえた方法で西欧社会にその怒りを解放し、屈辱をそそぎたい。その機会を虎視眈々(こしたんたん)と狙っているのだ。それを大英帝国という宗主国の罪悪感の反映とみなすのは、俗っぽい心理学だろう。こういう解釈に乗っかれば、E・A・ポオの「あの作品」(あえて伏す)も「猿の手」のひとつのバリエーションといえる。もっとも、ポオはその「非合理」を西欧的な「合理」でもういちど征服(再植民地化)してしまうのだが(一見、そのように読める)。
同様の系列に、モーパッサンの「手」(1883)がある。
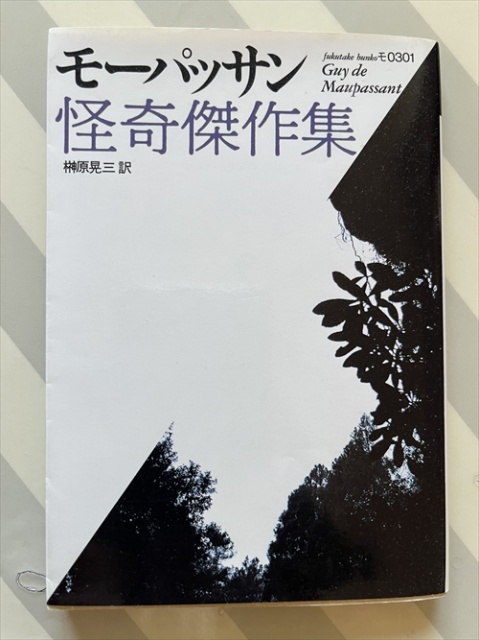
(『モーパッサン怪奇傑作集』福武文庫)
モーパッサンは19世紀の代表的な写実主義、自然主義の作家だ。非合理的で超自然的な恐怖小説、ホラージャンルに手を染めているとは、意外である。この本を昔、書店で見つけたとき、わたしはそう思った。その感想はあながち、まちがいではない。モーパッサンの「怪奇小説」は幽霊や妖怪、怪物の暗躍する、いわゆる単純な「非合理的な物語」ではないからだ。「手」は次のような話である(結末まで内容に触れます。未読の方はご注意を)。
上流階級の貴顕がそろうパリのサロン。予審判事の老人がかつて体験した犯罪事件について貴婦人たちに語り出す。この貴婦人たちは「謎めいた事件」が大好きで、好奇心をそそられるらしい。現代風にいえば、「ワイドショー的関心」だろう。しかし、この老人の意見では「超自然などない。犯行が念入りに計画され、不可解なだけだ」となる。
彼はかつて、赤毛のイギリス人と親交をもった。このイギリス人はアメリカ、インド、アフリカを旅行し、そこで「人間狩り」をやったと自慢する。彼の家には、「人間の手」が展示されている。前腕の途中から斧か鉈(なた)で断ち切られた、干からびた黒い手だ。手首には太い鎖が巻きつけてあり、それは壁にしっかり固定されていた。
「この鎖は必要ないでしょう?」と予審判事。
「いえ。必要です。この『手』はいつも逃げたがっていますから」
(気が狂っているのか)と老人は正気を疑う。イギリス人の家には装填された銃が3丁もあり、つねに身の危険を意識しているらしい。
1年後、このイギリス人が絞殺される。
首には五本の指の跡。壁に固定された「手」は消えてなくなっていた。しかし、その指の1本は被害者が噛み切ったらしく、口のなかから発見される。
使用人は次のように供述した。
「1ヶ月前にきた手紙を読んでから、ご主人様はようすが変でした。壁に固定された『手』を鞭ではげしく打ち、夜中には誰かと話しているようで、ひそひそ声が聞こえました。ときどきは、大声で言い争いしていたみたいです。いつも不安で、なにかに腹を立てているようでした。かならず銃を手元におき、離しません。事件の当日は妙に静かで、不審に思い、書斎に入ってみると、このありさまでした」
事件は未解決で、犯人はいまだにつかまっていないという。
話を聞き終えた貴婦人がいう。
「怖い。いったい、どう解釈なさっているのですか?」
予審判事はそっけなく、応じる。
「とてもかんたんです。『手』の持ち主が復讐にやってきたのです。残った片手で絞め殺し、自分の片手を奪い返したのですな」
婦人は小声でつぶやく。
「いえ。そんなはずありません……」
以上があらすじだ。まるで、ポオの「あの作品」とジェイコブズの「猿の手」の、ちょうど中間に位置するようなストーリーである。予審判事は植民地アメリカ(合衆国はすでに独立しているが、テキストには「アメリカ」とあるだけだ。北米ではなく、中米や南米かもしれない)からの非合理な反撃を、合理によって再反撃(再植民地化)する。しかし、サロンの貴婦人はそれをもういちど非合理に送り返そうとこころみる。真相は「藪の中」だが、写実主義の作家が恐怖小説を書くとこうなるのか、と妙に感心し、納得した。
手や腕はテリトリー空間の集約ポイントのひとつである。以前、コンラート・ローレンツの『攻撃』を採り上げ、動物や昆虫のテリトリー時空間について述べたことがある(第6回 ソロモンの指輪)。自力で動く生物にはテリトリーが存在する。目に見えないため研究対象になりにくいが、これは非常に重要な概念だ。このテリトリーが外敵に侵犯されたとき、生物は攻撃スイッチがオンになる。そのとき、重要になる集約ポイントはみっつある。目、手、口だ。
目は外敵の動きに注目し警戒し、あわせて自分に攻撃の意図があることを匂わせ、威嚇する。口はうなり声、吠え声などの威嚇や、噛みついたり食いちぎったりといった実際の攻撃に利用される。人間なら「話す」ことで不快感や不信感、攻撃の意図を相手に伝えられる。そして、手や腕は相手の攻撃を防ぎ、殴ったり叩いたり、自ら攻撃する場合、有効に機能する。
日本語でも「腕が鳴る」「腕をふるう」「すぐれた手腕」という。これらの「腕」は身体の「肢」の意味をはなれている。ものごとをなしとげる力、力量、技術、技能だ。英語ではarm=武器、army=軍隊、armor=甲冑(かっちゅう)と、よりはっきり「戦う」用語になっている。
つまり、テリトリーを守るための「腕」の延長が棍棒であり、剣であり、槍である。それは弓矢となってテリトリー空間を延長した。さらに銃、大砲、ミサイル、ICBM(大陸間弾道ミサイル)と極度にテリトリーの距離を伸ばしている。
1911年には、すでにイタリアがトルコに対し、飛行機から手榴弾を投下する攻撃をおこなっていたという。第1次世界大戦では、航空機が戦場で活躍した。戦闘用の飛行機が人口の密集する都市上空に飛来し、爆弾を地上に落とした。これも「長く伸びた腕」であろう。
1924年に発表されたある恐怖小説には「指紋を残す幽霊」が登場する。ネタバレを避けるため、この作品のタイトルにはあえて触れない。あらすじは次のとおりである。
ロンドン郊外の貸別荘で冬を過ごす男が主人公だ。大雪の夜の11時ごろ、家の外で車が停まる音を耳にし、彼はいぶかる。幹線道路から離れた、交通量の極端に少ない田舎なのだ。ようすを見るため外に出てみると、自動車がエンジントラブルに見舞われたらしい。運転していた女の子がかんかんに腹を立てている。「車は動かないから、今夜一晩、家に泊まったらどうか」と親切心から提案したが、彼女は「ひとりで歩いて帰る」と無理をいう。途方に暮れていると、牛乳配達のタンクローリーが通りかかる。奇跡だ。タンクローリーの運転手は「いいよ。街までのっけていってやるよ」と気安く、女の子に約束する。彼女の車を別荘のガレージ入れると、3人とも身体がすっかり冷えてしまった。
「少しくらいならかまわない」と運転手が言うので、彼はふたりを居間に招じ入れ、酒をふるまう。
身体があたたまったふたりが別荘を出発した後、「こんな夜中にこんなへんぴな土地を若い女の子がひとりでドライブしているなんて、どう考えても変だ」と彼は思い直す。そこでガレージに収納した彼女の車を点検することに。
ドアを開けたら、男の死体が転がり出した。背中を銃で撃たれている。別荘には電話がない。明日、警察に知らせようと彼はその晩、寝てしまう。
朝、ガレージを確認すると、車が消えている。もちろん、車内にあった死体もない。「夢か?」と思うが、居間には昨日の夜、ふたりが酒を飲んだグラスが残っていた。グラス表面には指紋がしっかり付着している。「殺人事件が起こったのだ。この指紋は重要になる」 そう考え、ビスケットの缶にグラスをしっかり保管し、彼は列車に乗ってロンドンへ。スコットランド・ヤードに旧知の刑事がいるのだ。
指紋を鑑定してもらうと、結果は3分で出た。友人の刑事は言う。
「その女の子は有名な不良グループのメンバーだ。敵対するグループと派手な喧嘩になり、死人が出たんだ。彼女は撃たれた友達を車に運び込んで逃走したが、途中でエンジンがだめになった。そこで誰かの家のガレージに車を残し、途中でつかまえたタンクローリーに同乗した。ところが、そのタンクローリーはスリップ事故を起こし、ふたりとも車から飛び出し、煉瓦塀に頭をぶつけ、首の骨を折って死んでしまった。以上が真相だよ」
彼は仰天する。
「ひゃあ。君たちはすごく優秀だな! つい昨日の出来事なのに、そんな細かいところまでわかっちまうのか!」
「なに言ってんだ。これは1919年の事件だ。君が話したひとたちはみんな、5年前に死んでいるんだよ」
1919年の夜、時空の扉が突如ひらき、関係者(女の子とタンクローリーの運転手)が1924年にタイムスリップする。死体入りの車を主人公のガレージに収め、ふたたび1919年に舞い戻ってスリップ事故を起こした(スリップ、スリップと紛らわしくて申し訳ない)。そういう解釈も可能かもしれない。だが、ここは素直に怪奇小説の文脈で考え、女の子も運転手も幽霊だったとみなそう。すると、この幽霊は「指紋」を残したことになる。
エンストした車も実体がなかった幽霊車だ。これを主人公はガレージに押し入れている。つまり、物理的な存在感があったのだ。女の子がグラスを「握った」のなら、指紋も当然、付着するわけだ。
かつて小松和彦は鬼と幽霊を次のように定義した。
「鬼は魂が消え、肉体が残った状態。だから、人間性を失っている一方で、実体感があり、物理的な暴力をふるうことができる。対して幽霊は、魂が残っているが、肉体を失った状態。恨みや後悔、肉親への愛情、現世への執着心といった人間的な感情を持っているが、実体感は希薄である。足がなかったり、姿が透けていたり、声しか聞こえなかったりする」
記憶で書いている。出典をさぐってみたが、ちょっと分からない。
この整理、ある程度、正確に思える。
小松は日本の怪異、妖怪、神霊の研究から以上の定義を導いたのだろうが、「人間性をもった霊魂は肉体性に乏しい」というイメージ、西欧でも共通だと思う。たとえば、ホメロスの『オデュッセイア』だ。故郷イタケをめざし、地中海を漂流するオデュッセウスは冥界に迷い込む。そこで亡き母と再会し、喜びのあまり身体を抱きしめようとするのだが、果たせない。姿が見え、声も聞こえるのに、実体ではないのだ。そこに出現しているのは映像だけ。つまり、幻だ。
「母のこの言葉に、わたしは心の内で、世を去った母の霊をこの腕に抱きたいと思い、抱こうと心が逸(はや)るままに、三たび母に駆け寄ったが、三たびとも母は影か夢にも似て、わたしの手をふわりと抜けてしまう。」(松平千秋訳)


(ホメロス『オデュッセイア』岩波文庫)
また、ダンテの『神曲』でも同様の描写を読んだ記憶がある。煉獄篇だったと思うが、そこでは亡者に影ができないのだ。姿は見えているが、実体がないので、太陽光線が透過してしまうのである。手もとにないので、書影はありません。
「指紋」を残す幽霊は、西欧世界でも「幽霊らしくない幽霊」のはずなのだ。幽霊とは、テリトリー概念に引き寄せて考えると、テリトリー時間の延長である。テリトリーは一般に空間の概念だ。しかし、わたしたちは時空連続体のなかで生活している。つまりテリトリーとは、正確にはテリトリー時空間なのだ。
肉体的な寿命が尽きた後でも、テリトリー時間を延長することは可能だ。生き残った後世のひとたちがその存在を忘れず、語りつづければ、テリトリー時間は伸びつづける。「幽霊」「亡霊」はそうやって延命する(すごく大ざっぱに考察しています)。しかし、そこには「空間=実体」がないのである。
一方、指紋とは「空間的実体(の痕跡)」だ。幽霊の指紋とは、死の世界から現世に影響を及ぼそうとする恐怖や恐慌の刻印に他ならない。それは「長い、長い腕の先の指」であり、何か恐ろしいもの――死をもたらす。たとえば「冷戦」という過去の亡霊はどこかの国で生きつづけ、その「長い指先」で刻印すべき場所を今だに探っているらしい……。
(了)
大森葉音(おおもり・はのん)
北海道生まれ
本格ミステリ作家クラブ会員
作家。2000年に「大森滋樹」名義で「物語のジェットマシーン―探偵小説における速度と遊びの研究」で第7回創元推理評論賞佳作入選。
探偵小説研究会に所属し、ミステリの評論活動をはじめる。『ニアミステリのすすめ―新世紀の多角的読書ナビゲーション』(原書房)、『本格ミステリ・クロニクル300』(原書房)、『本格ミステリ・ディケイド300』(原書房)、『日本探偵小説を読む』(北海道大学出版会)、『日本探偵小説を知る』(北海道大学出版会)に共著者として参加。現在、北海道新聞日曜書評欄「鳥の目虫の目」を3~4か月に1度、持ち回りで執筆している。
2013年に「大森葉音」名義でファンタジー小説『果てしなく流れる砂の歌』(文藝春秋)を上梓し、小説家としてデビューする。2015年には本格ミステリ『プランタンの優雅な退屈』(原書房)を刊行している。地元札幌の豊平川サイクリングコースを自転車で走り回るのを楽しみとする。
X(旧ツイッター):https://twitter.com/OmoriHanon









